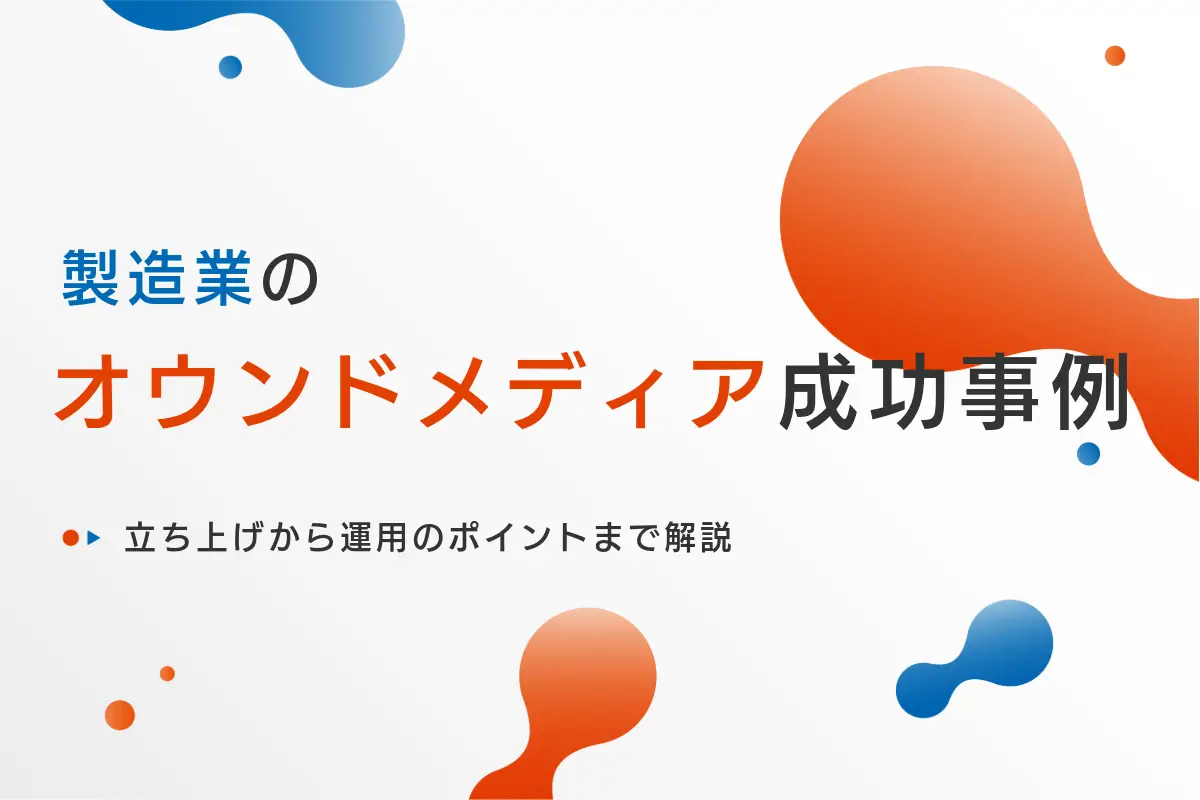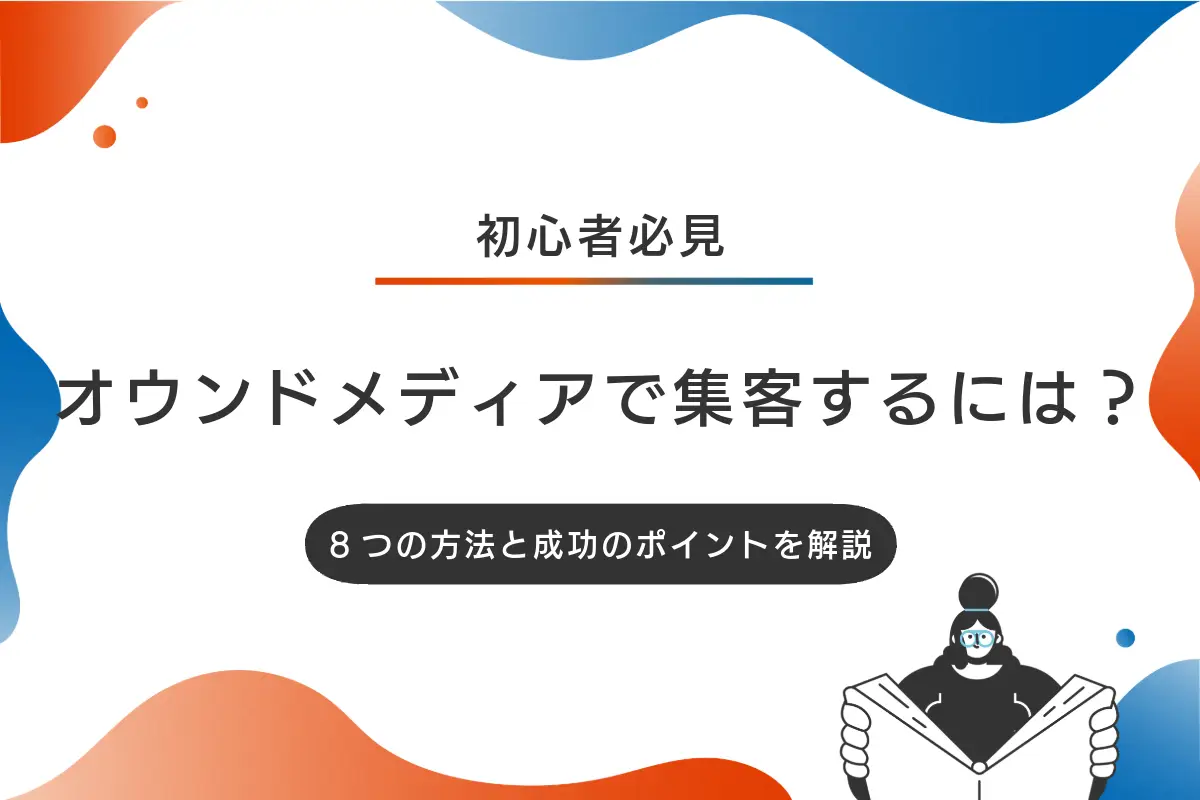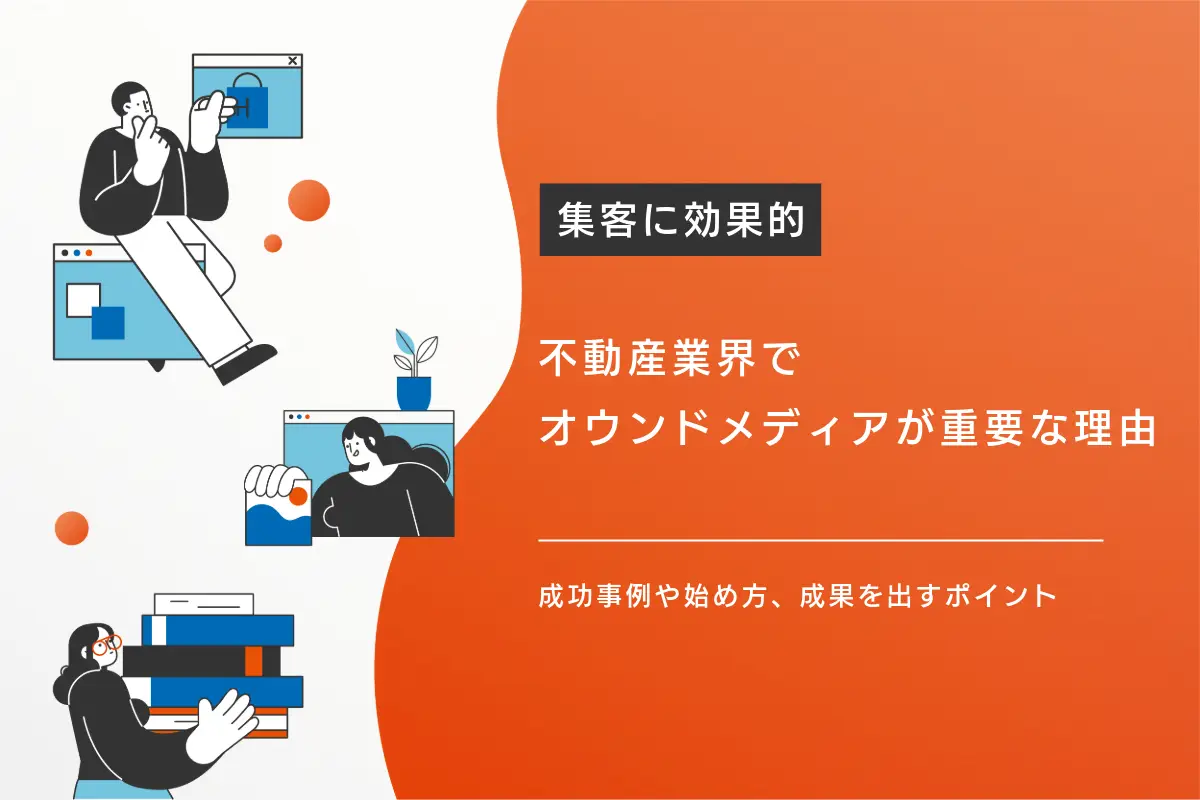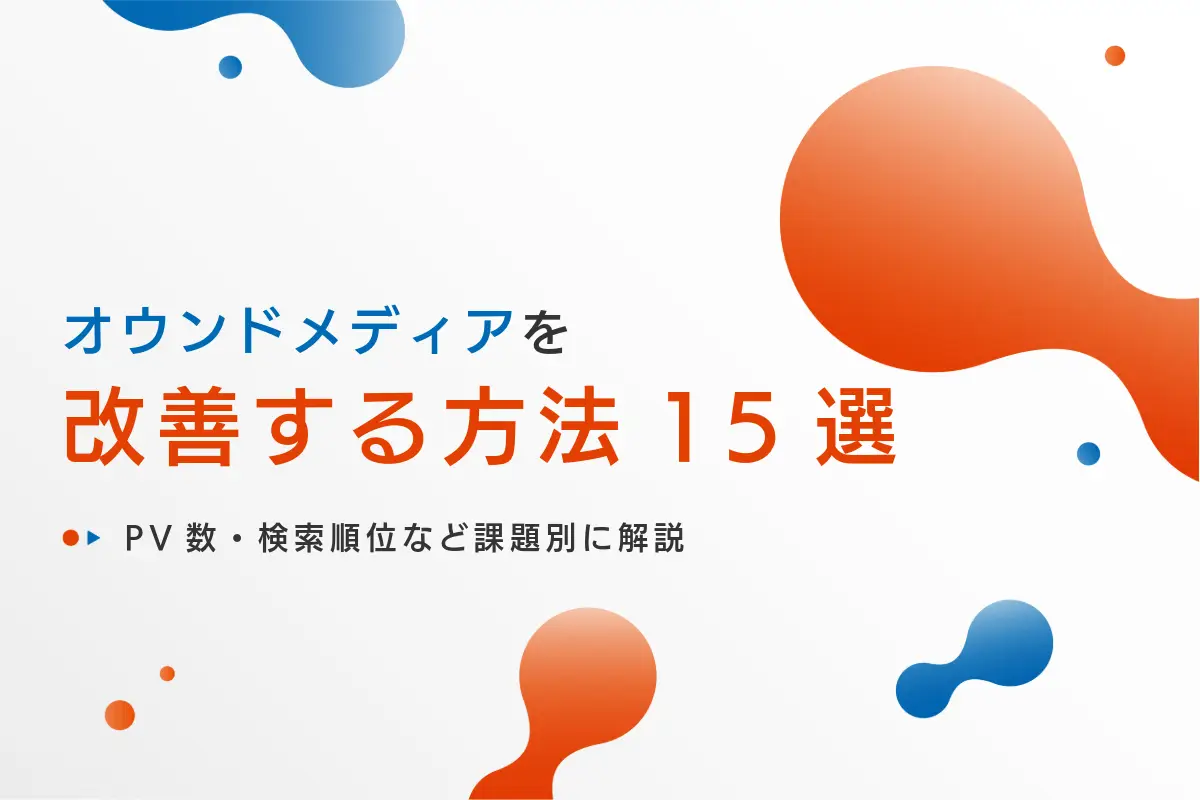オウンドメディアの分析方法を解説!役立つツールや見るべき指標とは?
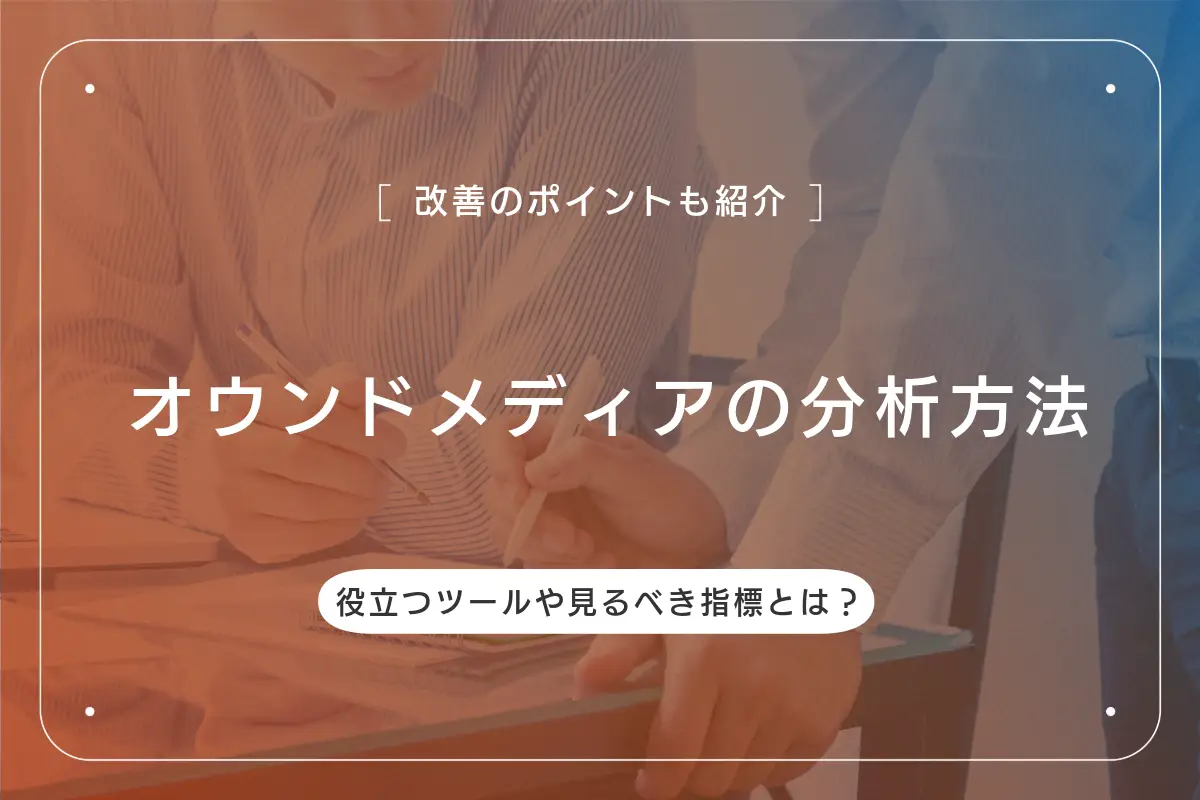
オウンドメディアの運営で目的を達成するには、定期的な成果の分析と継続的な改善が欠かせません。しかし、「どのような指標を分析すればよいのかわからない」「分析結果をどう活用すればよいのかわからない」と悩んでしまう企業は多いものです。
この記事では、オウンドメディアの分析方法や重要な指標について詳しく説明します。分析に役立つツールと改善のポイントも紹介しているので、より効果的なメディア運営に活用してみてください。
関連記事:オウンドメディアのメリット・デメリットは?失敗しないための対策法も解説
オウンドメディアの分析が重要な理由
オウンドメディアの分析が重要な理由として、以下の2つが挙げられます。
目標達成のため
方向性を見直すため
それぞれどのようなことなのか、詳細をみていきましょう。
目標達成のため
オウンドメディアの分析は、目標達成のために欠かせません。
各コンテンツの閲覧状況や成果につながった割合を分析すると、どのようなアプローチが有効だったのかを見極めやすくなります。効果的な施策がわかれば、投資対効果(ROI)を高めるためのヒントを得られるでしょう。
特に分析しておきたいのは、コンテンツの反響やユーザーの行動パターンです。「どの記事がよく読まれているのか」「どの導線で成果につながっているのか」を把握できれば、より効果的なキーワードの発見や今後の戦略立案に活かせます。
分析を通じて「勝ちパターン」を見つけ出すことで、コンテンツマーケティングの成果を最大化しやすくなるでしょう。
方向性を見直すため
オウンドメディアの分析は、メディアやコンテンツの方向性を見直すときにも重要になります。「オウンドメディアが成果につながっているか」「内容はユーザーニーズに沿っているか」を知ることで、軌道修正を行いやすくなります。
オウンドメディアを運営するときは、企業が伝えたい情報を一方的に発信するだけでは、十分な成果は得られません。分析を通じてユーザーの関心や課題を把握し、それに応えられるコンテンツを提供することが何よりも重要です。
顧客理解を深めて本当に価値のあるコンテンツを提供するためにも、継続的な分析と改善は欠かせないのです。
オウンドメディアの分析に役立つツール
オウンドメディアの分析は、ツールを活用すると効率的に行えます。分析に役立つツールにはさまざまなものがありますが、ここでは代表的なものを5つ紹介します。
Googleアナリティクス(GA4)
Googleサーチコンソール
GRC
User Heat
Ahrefs
それぞれどのようなツールなのか、詳しくみていきましょう。
Googleアナリティクス(GA4)
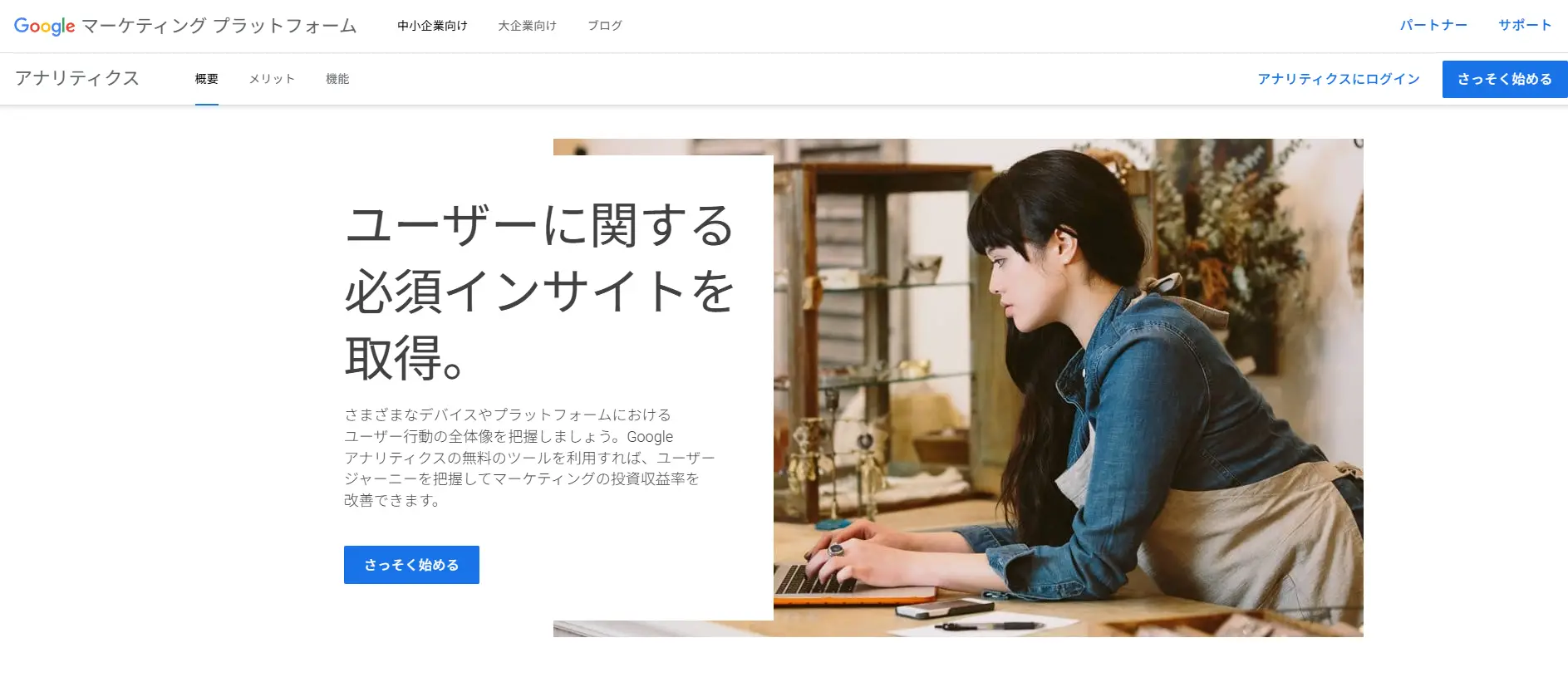 ▲出典:Googleアナリティクス
▲出典:Googleアナリティクス
Googleアナリティクス(GA4)は、Googleが提供するアクセス解析ツールです。アクセス数やユーザーの行動パターン、流入経路などさまざまなデータを無料で取得できます。
オウンドメディアの効果測定に必要な指標は網羅しているので、基本的な分析はGA4だけでも十分です。ただし、設定や操作に一定の知識を要するため、高度な分析を希望する場合は専門家に相談することをおすすめします。
Googleサーチコンソール
 ▲出典:Googleサーチコンソール
▲出典:Googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、検索エンジンからの流入状況を分析できる無料ツールです。検索クエリやクリック率、表示順位などの情報を取得できます。
Googleサーチコンソールは、GA4とセットで導入しておきたい必須のツールです。GA4が「アクセス後の行動や数値」をメインに分析するツールであるのに対して、サーチコンソールは「アクセス前の数値」をメインに分析するツールという違いがあります。
GRC
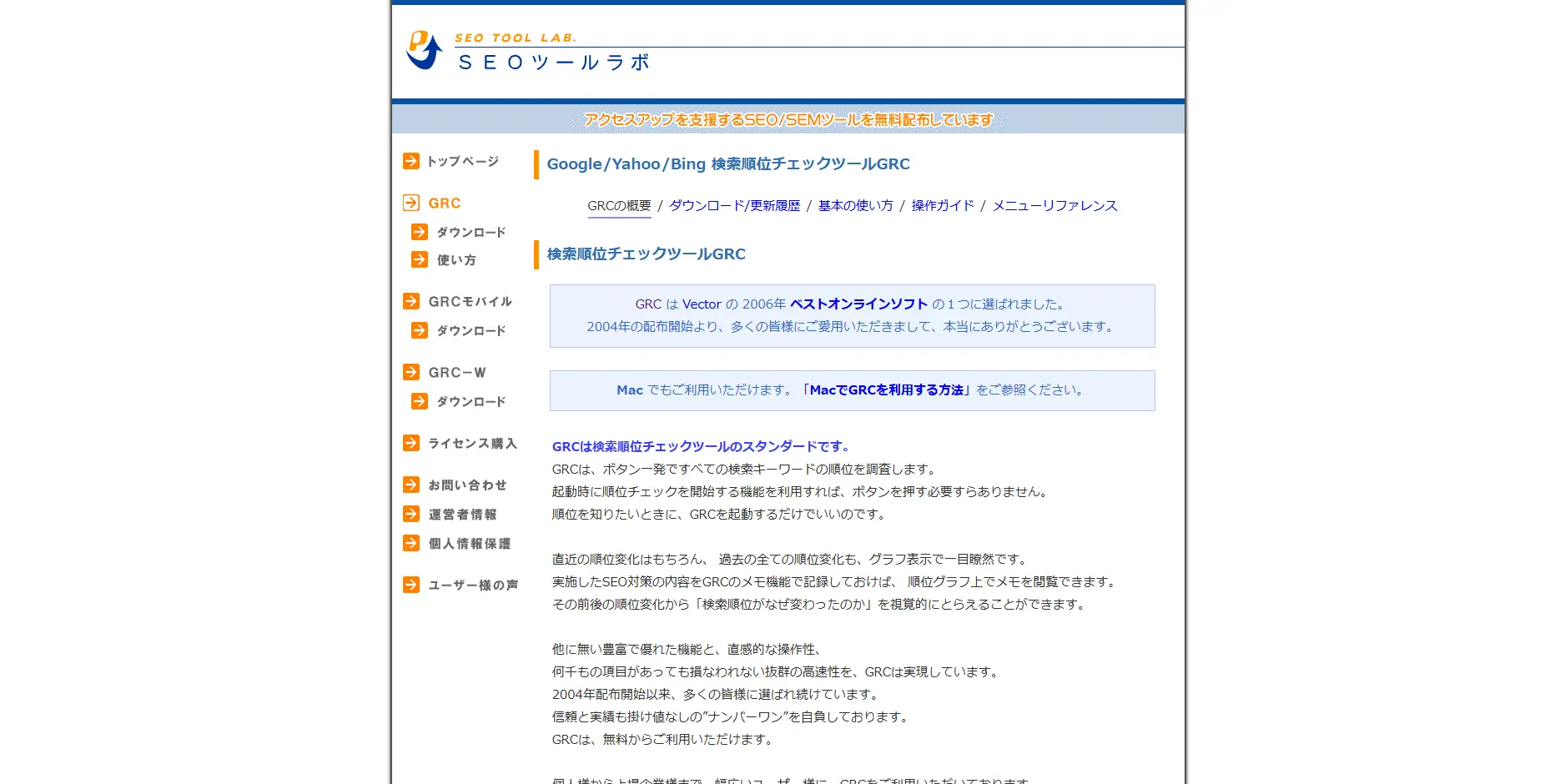 ▲出典:GRC
▲出典:GRC
GRCは、記事の検索順位を解析するためのツールです。記事のURLとキーワードを登録しておくと、検索順位の変化を表示してくれます。
有料ツールですが、自社コンテンツが検索エンジンにどれくらい評価されているのかを一目で把握できるので、利用する価値は十分にあるでしょう。他のツールに比べると機能がシンプルで、安価かつ簡単に利用できます。
User Heat
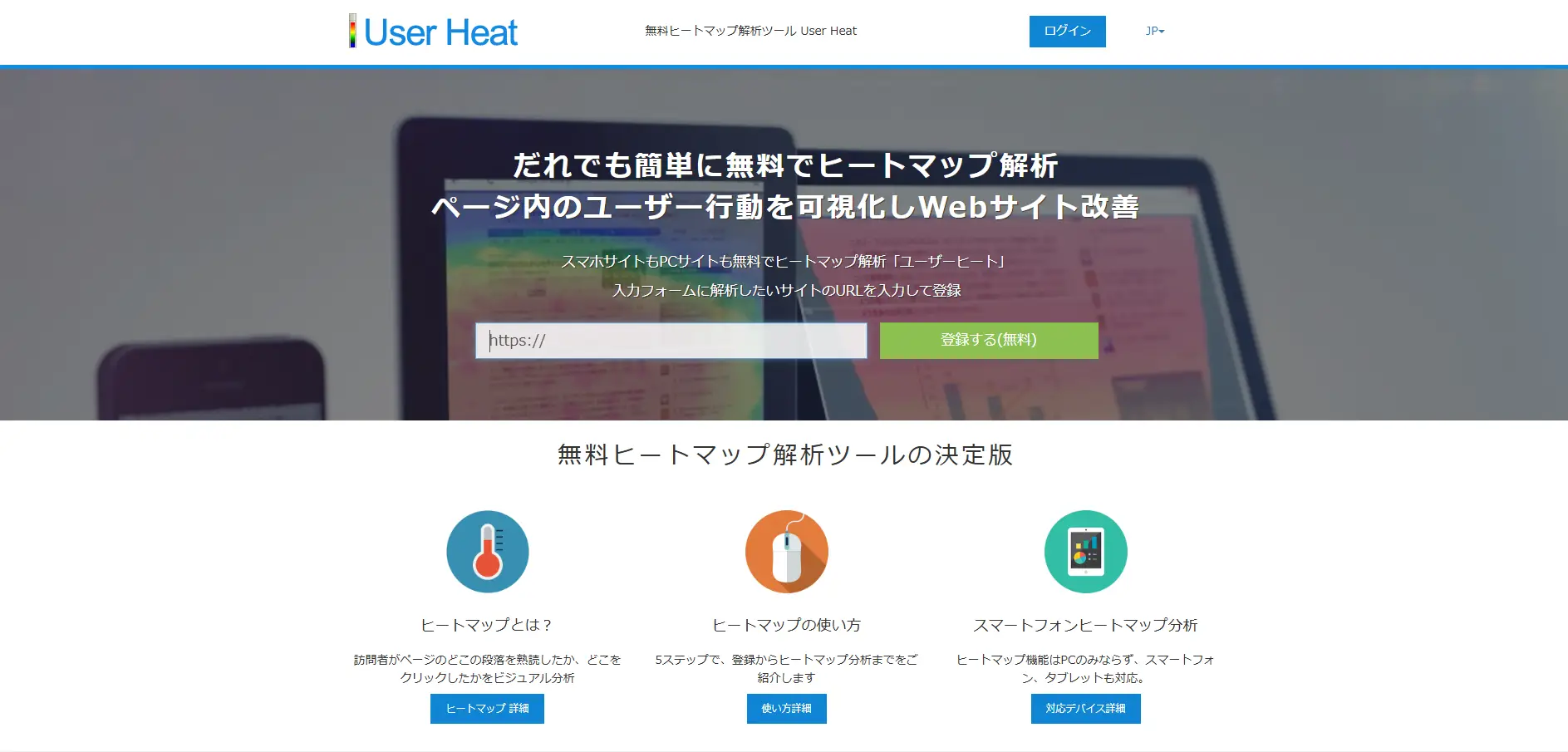 ▲出典:User Heat
▲出典:User Heat
User Heatは、ユーザーの行動を可視化できるヒートマップツールです。ユーザーが熟読しているエリアやクリック箇所、離脱エリアなどを一目で把握できます。
ヒートマップを使うと、アクセス解析の数値データだけではわからない問題点を発見可能です。無料で利用できますが、大規模サイトの分析を希望する場合は、有料版のUser Insightを利用したほうが便利です。
Ahrefs
 ▲出典:Ahrefs
▲出典:Ahrefs
Ahrefsは、世界中で導入されている高機能な有料SEO分析ツールです。自社サイトはもちろんのこと、競合サイトの分析を行うことも可能です。
順位変動の記録やキーワード選定、被リンク分析なども行えます。AIを使ったライティングツールも提供されているので、分析だけではなくコンテンツ制作にも役立つツールをお探しの企業におすすめです。
オウンドメディアの分析で重要な指標と改善策
オウンドメディアを分析するときに重要な指標として、以下の7つが挙げられます。
PV数
UU数
滞在時間
セッション数
検索順位
CVR
シェア数
ここでは、各指標の意味と改善のヒントを紹介します。
なお、オウンドメディアの改善についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:オウンドメディアを改善する方法15選|PV数・検索順位など課題別に解説
PV数
ページビュー(PV)数は、サイトの各ページが閲覧された回数を示す指標です。
PV数が多いほど、そのページが多く見られていることになります。ただし、「PV数が多いコンテンツ=成果が出ているコンテンツ」とは限らないので、他の指標と組み合わせながら分析することが重要です。
PV数を改善するには、以下のような施策が効果的です。
SEOを強化して検索流入の増加を狙う
SNSで記事をシェアする
メールマガジンで記事を紹介する
関連記事の内部リンクを設置して回遊性を向上させる
UU数
ユニークユーザー(UU)数は、実際にサイトを訪問した人数を示す指標です。
同じユーザーが複数回訪問してもカウントは1回となるため、実質的なリーチ数を把握したいときにチェックしましょう。PV数とUU数を比較することで、リピーター率を分析できます。
UU数の改善には、以下のような施策が有効です。
ターゲット層に向けて広告配信する
検索意図に合致したコンテンツを提供する
SNSを活用してメディアの認知度を向上させる
外部メディアとの連携を強化する
滞在時間
滞在時間は、コンテンツの質やユーザーの興味を測れる重要な指標です。
滞在時間が長いページは、ユーザーにとって価値のある情報を提供できていると考えられます。逆に、滞在時間が短いページは、コンテンツの改善や構成の見直しが必要かもしれません。
滞在時間の改善には、以下のような施策が有効です。
読みやすい文章構成と適切な見出し設定を心がける
図表やイラストを用いて視覚的な情報も提供する
動画コンテンツを活用する
ステップ形式で情報をわかりやすく整理する
セッション数
セッション数は、ユーザーがWebサイトにアクセスしてから離脱するまでの回数を示す指標です。
同じドメイン内であれば、どのページを表示してもセッション数は1になります。ただし、一定時間アクションがない場合や日付をまたいだ場合は、セッションのカウントが途切れます。
セッション数は、ユーザーがサイト内のページをどれくらい閲覧しているのかを示す「回遊率」と、ユーザーが特定のページだけを閲覧して離脱した割合を示す「直帰率」とセットで分析することをおすすめします。複数の指標を組み合わせることで、サイトの導線設計やコンテンツの魅力度を評価しやすくなります。
これらの指標を改善するには、以下のような施策が有効です。
関連記事を適切に配置する
ユーザーの興味・関心にもとづいて記事を表示する
導線設計を見直す
モバイルファーストデザインを採用する
検索順位
検索順位は、特定のキーワードにおける自社コンテンツの検索位置を示します。
上位表示されるほど多くのユーザーの目に触れる可能性が高まるので、検索流入の増加につながります。検索意図に合致したコンテンツに仕上がっているかどうかも、この指標から判断可能です。
検索順位を改善するためのポイントは、以下のとおりです。
しっかりとキーワード戦略を立てる
ユーザーの検索意図に応えられる質の高いコンテンツを制作する
内部リンクを最適化する
サイトの表示速度を改善する
モバイルフレンドリーな設計にする
CVR
CVR(コンバージョン率)は、サイト訪問者のうち、実際に資料請求やお問い合わせなどの目的の行動(コンバージョン)を取った割合を示します。オウンドメディアの最終的な成果を測る重要な指標であり、投資対効果(ROI)を判断する際の基準となります。
CVRの改善には、以下のような取り組みが効果的です。
コンバージョンまでの導線を最適化する
適切なタイミングでCTAを設置する
ユーザーの不安や疑問を解消する情報を積極的に提供する
フォームの入力項目を簡素化する
ABテストを実施する
シェア数
シェア数は、SNSなどでコンテンツが共有された回数を示す指標です。コンテンツの価値や共感度を評価したいときに役立ちます。
また、どのような内容がユーザーの興味を喚起するのかを把握する手がかりにもなります。
シェア数を増やすための施策例は、以下のとおりです。
SNSのシェアボタンを設置する
共感性の高いコンテンツを制作する
トレンドを反映したコンテンツを制作する
画像や動画を活用する
オウンドメディアの分析を成功させるコツ
オウンドメディアの分析をしっかりと成果につなげるには、以下のようなコツを意識することが大切です。
KPIを設定しておく
「仮説→検証」を繰り返す
分析のタイミングを決めておく
オウンドメディアのプロに相談する
各項目の詳細をみていきましょう。
KPIを設定しておく
効果的な分析を行うには、適切なKPIの設定が不可欠です。最終的な目標(KGI)達成までの道筋を示すKPIがあることで、オウンドメディアの効果や方向性を把握しやすくなります。
KPIを設定するときは、短期的なKPIと長期的なKPIの両方を決めておきましょう。異なる時間軸で数値目標を設定すると進捗管理の精度を向上させられますし、小さな成功体験を積み重ねれば、モチベーションを維持しながら着実な目標達成を目指せます。
それぞれに適したKPIの一例として、次のようなものが挙げられます。
短期的なKPI |
|
長期的なKPI |
|
KPIを設定するときは、現状を正確に把握したうえで、達成可能な目標を設定することが大切です。
関連記事:コンテンツマーケティングのKPIを設定する手順|目的別の具体例や管理のポイント
「仮説→検証」を繰り返す
分析から得られたデータを効果的に活用するには、「仮説→検証」のサイクルを回すことが重要です。
例えば、特定のページで直帰率が高くなっている場合は、「導入文が長すぎて本題に入る前にユーザーが離脱している」という仮説が立てられるかもしれません。この場合、導入文を短くすることで、直帰率が改善される可能性があります。
単に数字を追うだけでは、本当の意味での課題解決にはつながりません。データからみえてくるユーザーの行動やニーズを理解し、「なぜこのような結果になったのか」「どうすれば改善できるのか」という視点で仮説を立てることが大切です。
分析のタイミングを決めておく
効率的かつ効果的にオウンドメディアの分析を行うには、実施のタイミングを決めておくことをおすすめします。
例えば、PV数やコンバージョン数は毎日確認して、主なKPIの達成状況や人気コンテンツの分析は毎週末に行います。月末にはより詳しいアクセス解析や競合分析、コンテンツの評価・改善を実施するとよいでかもしれません。
日次・週次・月次など、指標の特性に応じて適切な確認頻度を設定しておくことで、データの比較や傾向の把握を行いやすくなります。また、分析作業をルーティン化することで、異常値の早期発見や迅速な対応も可能になるでしょう。
オウンドメディアのプロに相談する
オウンドメディア運営の経験が少ない企業の場合、分析結果から適切に課題を抽出したり改善策を立案したりすることが難しい可能性があります。たとえデータを取得できたとしても、数値が持つ意味や活用方法がわからず、効果的な改善策を立案できないケースは珍しくありません。
オウンドメディアの分析や改善を的確に行いたいのであれば、専門企業に相談しましょう。プロの支援を受けることで、最短で最大限の効果を得られやすくなります。
関連記事:オウンドメディアで外注できる業務とは?費用や効果、成果を出すためのポイントを紹介
関連記事:オウンドメディアの運用代行が得意な会社9選|失敗しない依頼先の選び方も解説
オウンドメディアの分析・運用はコンマルクにご相談ください
オウンドメディアの効果を最大化するには、適切な分析と継続的な改善が不可欠です。ぜひ今回紹介したツールや指標を、オウンドメディアの効果測定とより効果的な運用に活かしてみてくださいね。
社内にオウンドメディアを分析するノウハウやリソースが足りない場合は、オウンドメディアの運用を得意とする企業に相談するのも一案です。
オウンドメディアの分析・改善にお悩みの方は、株式会社GIGのメディア事業部が運営するサービス「コンマルク」までご相談ください。
コンマルクは、数百万PV〜数億PVのメディア構築実績を持つ専門家集団であるGIGのメディア編集部が、貴社の事業成長に必要不可欠なメディア運営を強力にバックアップするサービスです。オウンドメディアの分析から改善策の実行・内製化支援までワンストップでご提供します。
また、各種Webマーケティング施策やWebコンサルティングの実施にも対応。オウンドメディアを活用して事業の成長を加速させたい方は、お気軽にコンマルクまでご相談ください。
- SEOコンテンツ制作 / 設計
- インタビュー記事制作 / 設計
- ホワイトペーパー制作 / 設計
- アクセス解析・Webコンサルティング
- Web広告・SNS広告
- ペルソナ・カスタマージャーニーマップ設計
- コンテンツマーケティング伴走支援 など

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。