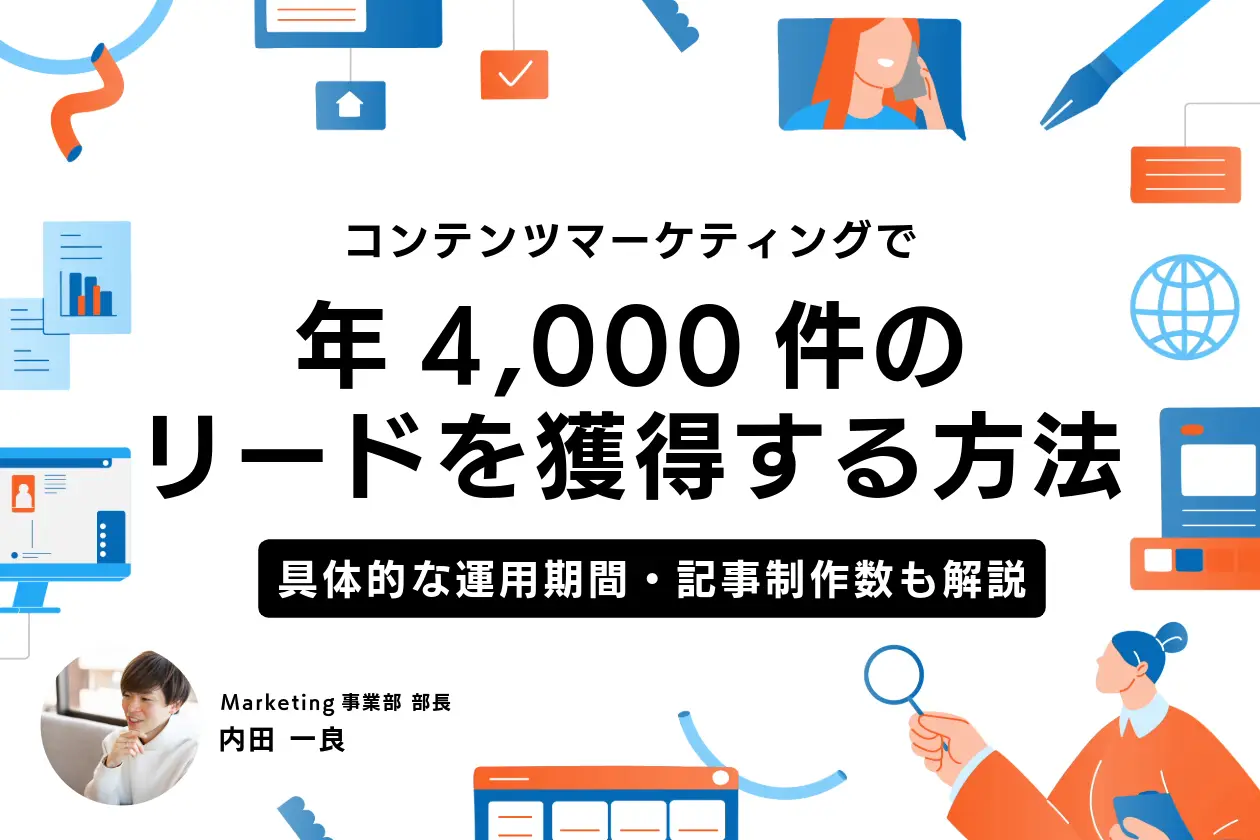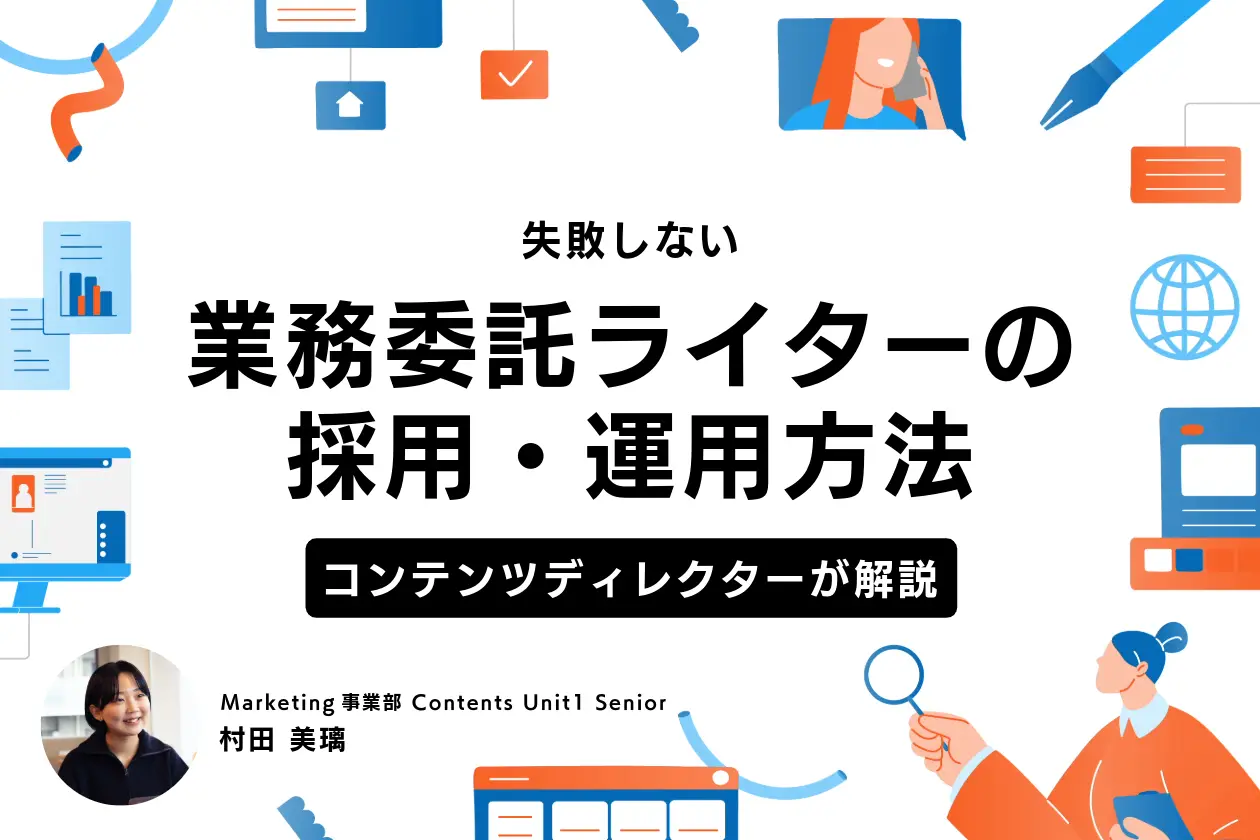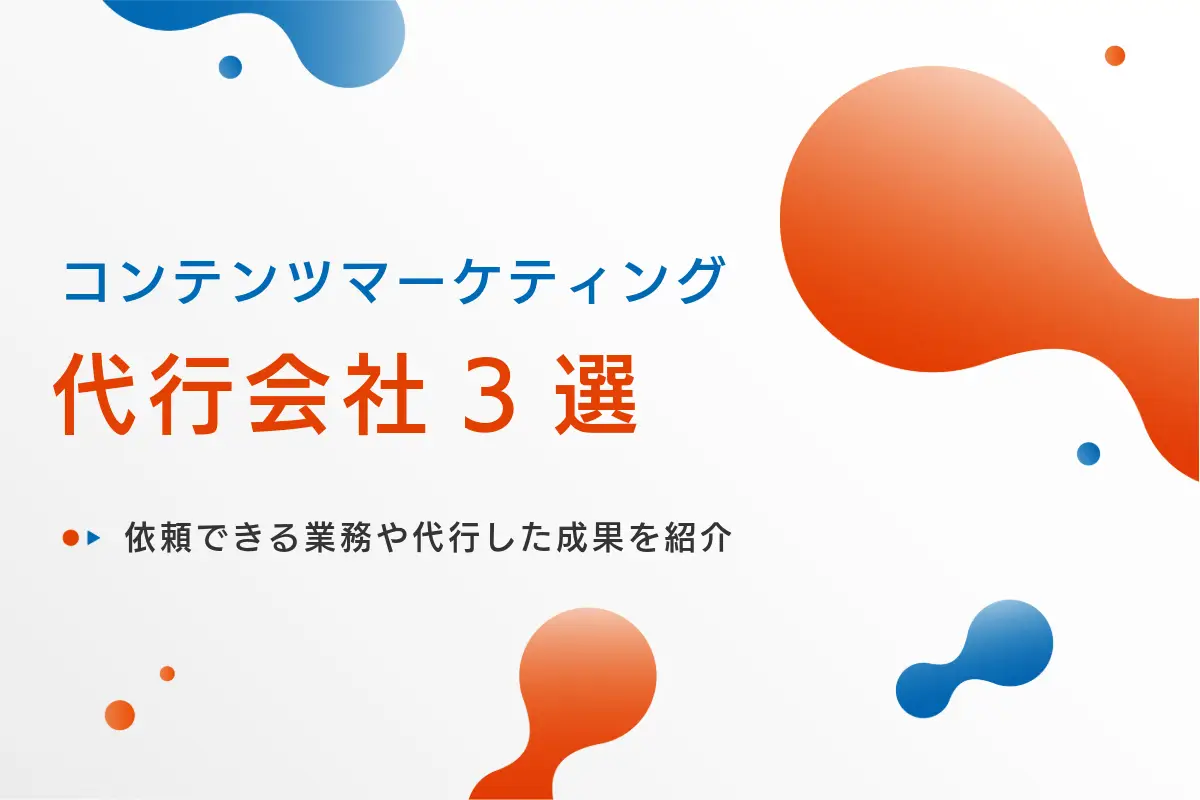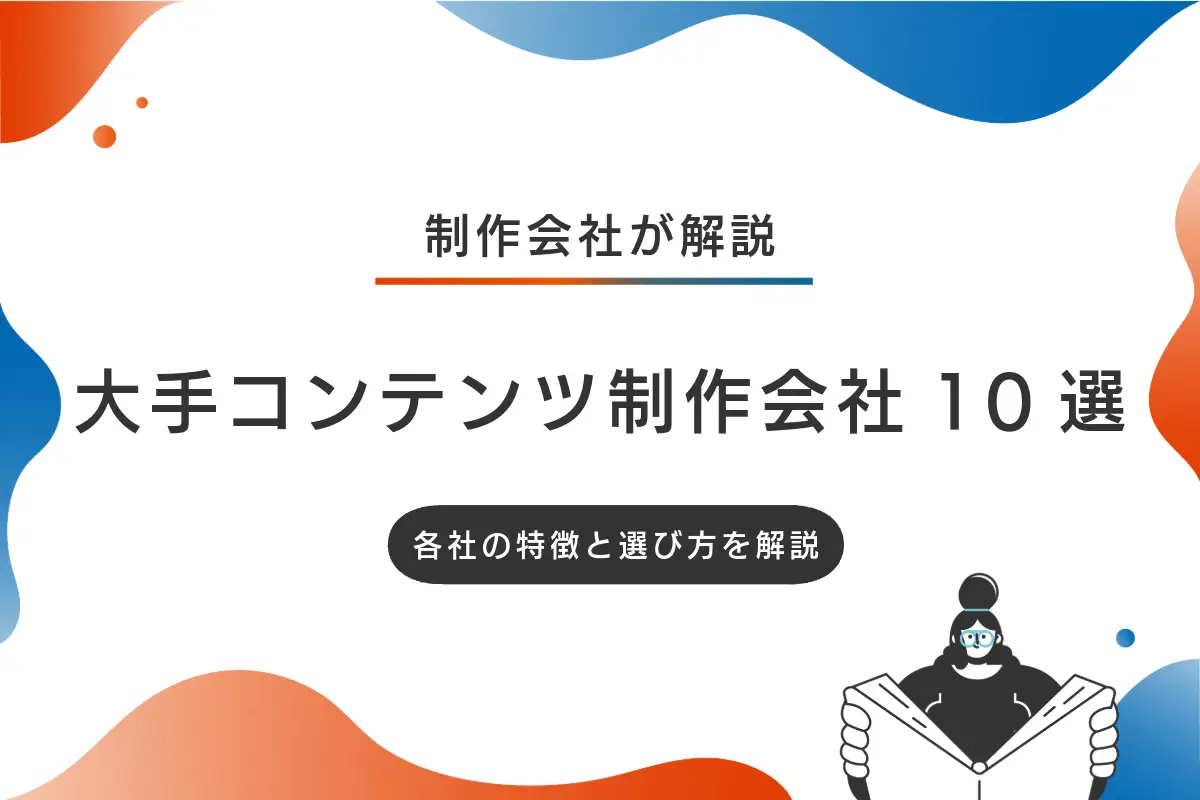記事制作の内製化(インハウス化)で失敗しない方法|業務委託の併用も解説
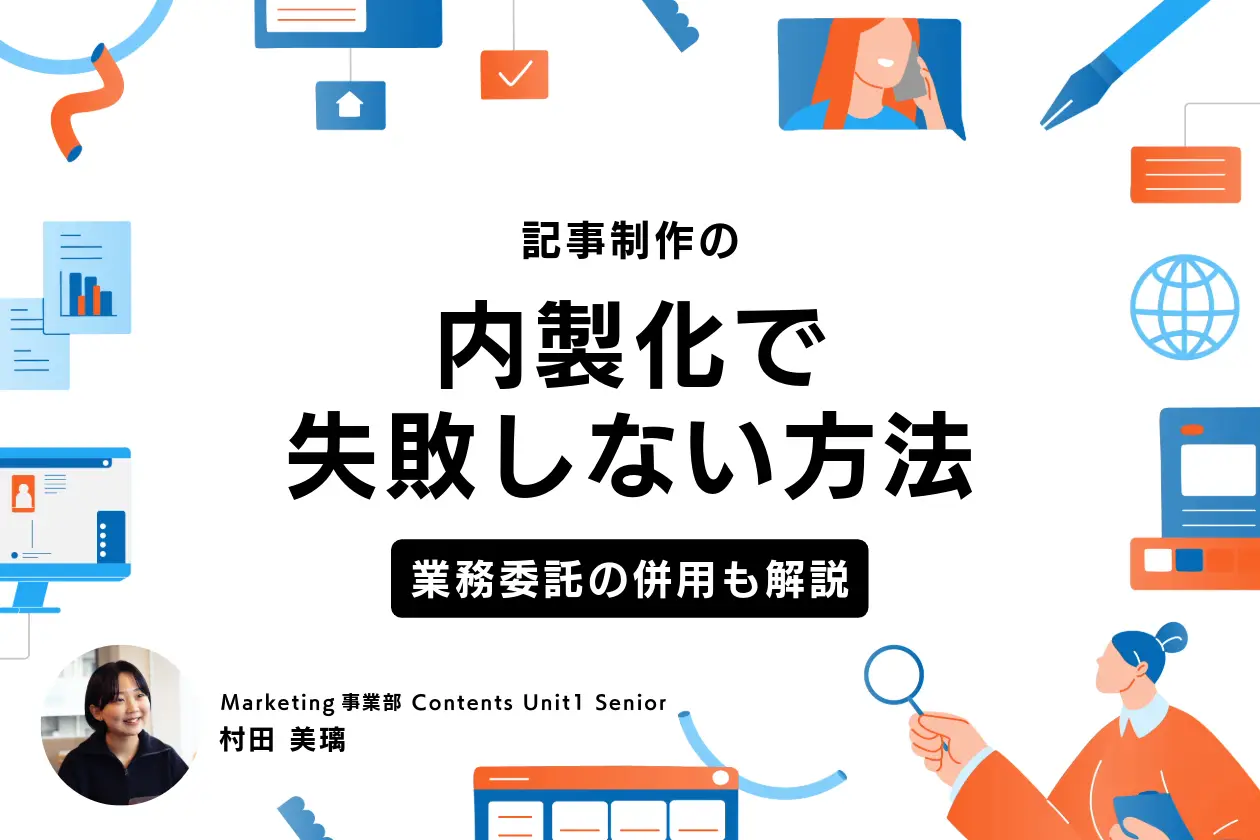
記事制作を内製化したいけれども、以下の悩みを抱えていませんか?
「記事制作を内製化したいけれど、何から手をつければいいか分からない」
「社内にリソースもノウハウもなく、成果が出る前に挫折しそうで不安…」
本記事では、10名ほどのライターと編集部を編成し、月40本累計500本以上の記事を作成した弊社(株式会社GIG)の村田が成果につながり、継続しやすい記事制作の内製化について解説します。
記事制作の内製化については、コンテンツマーケティング特化型eラーニングサービス「コンマルクアカデミー」でも詳しく解説しています。

村田美璃(むらたみり)
ファッション・ライフスタイルにまつわるWebメディアの編集者として、学生時代より記事制作にまつわる業務を広く経験したのち、2023年にGIGへジョイン。
前職では年間約500本の記事をディレクションし、現在は業種を問わずさまざまなお客様の取材コンテンツ制作(年間約120本)、ホワイトペーパー制作、SEO設計などを行う。
記事制作の内製化とは?
記事制作の内製化には以下2種類があります。
社内完結型:
企画から制作、公開、効果測定まで、すべてのプロセスを外部の力を一切借りずに自社のみで行うスタイルです。「インハウス」とも呼ばれます。業務委託併用型:
企画や戦略といった主導権は自社が持ちつつ、記事制作における専門的な部分(執筆、撮影、デザインなど)を、外部の制作会社やフリーランスといったプロフェッショナルに協力してもらうスタイルです。
関連記事:コンテンツマーケティングの支援会社21選|失敗しない選び方も解説
社内完結型と業務委託併用型のメリット・デメリット
社内完結型と業務委託併用型それぞれのメリット・デメリットは以下の表の通りです。
どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、企業の目的やフェーズに応じて使い分けることが成功の鍵となります。
タイプ | メリット | デメリット |
社内完結型 | 社内の人間しか知り得ない専門的な情報を発信できる | リソースの負荷が大きい |
業務委託併用型 | 効率的・継続的に記事を量産できる | 専門性が高すぎる内容には対応できない場合が多い |
カスタマージャーニーで考える最適な記事制作の内製化
社内完結型と業務委託併用型をどのように使い分ければ良いのでしょうか。顧客が商品やサービスを認知し、購入に至るまでのプロセスと照らし合わせると、それぞれの役割が明確になります。
▲社内完結型と業務委託併用型それぞれが適しているシーン
認知・集客フェーズ は業務委託併用型が有効
「〇〇とは」のような、一般的で検索ボリュームの大きいキーワードを狙う場合、つまり多くの人に興味を持ってもらうための間口の広い情報発信には「業務委託併用型」が適しています。
SEOやWebマーケティングの知見を持つ外部ライターの力を借りることで、質の高いコンテンツを効率的に制作し、安定した集客基盤を築くことができます。
興味・関心やナーチャリングフェーズ は社内完結型が有効
より専門的な知識を求めるユーザーやすでに自社サービスに関心を持っている見込み顧客に対しては、「社内完結型」が力を発揮します。
例えば、
現場の社員が執筆した専門的なノウハウ記事
開発者しか語れない製品の裏側にあるストーリー
といったコンテンツは、他社には真似できない信頼性と権威性を生み出し、顧客の興味関心を引きつけ、最終的な購買意欲を高める上で非常に有効です。
これらのニッチなコンテンツは検索される回数自体は少ない傾向にありますが、ホワイトペーパーとして配布したり、サイト内での回遊を促したりすることで効果を最大化できます。
なぜ業務委託併用型からのスタートがおすすめなのか?
これから記事制作を本格化させる企業には、まず「業務委託併用型」でスタートすることをおすすめします。その理由は以下の3つです。
目に見える成果に繋がりやすい
PV数やリード獲得数といった定量的な成果は、社内でプロジェクトの価値を証明する上で重要です。Webマーケティングの知見を持つプロの力を借りることで、成果に直結する質の高いコンテンツを効率的に制作でき、社内での協力も得やすくなります。
社内リソースの負荷が少ない
記事制作には、企画、執筆、編集、校正、入稿、効果測定など多くの工程が存在します。これら全てを限られた社内リソースで賄おうとすると、既存業務を圧迫し、担当者に過度な負担がかかる可能性があります。まずは負担の大きい「制作」部分を外部に委託するのが現実的です。
「質」と「量」を両立したメディア運営が可能になる
社内チームは「企画・戦略立案」に、外部パートナーは「制作」にそれぞれ集中することで、リソースを最適配分できます。これにより、コンテンツの幅(量)と深さ(質)のバランスを取りながら、無理なくメディアを運営していくことが可能になります。
業務委託併用型の体制構築
業務委託併用型の体制構築と役割分担について紹介します。コンテンツマーケティングは中長期的な施策のため、毎月コンスタントに記事制作ができる状態が理想です。
まずは月間8本公開できる体制を目指そう
まずは月間8本(年間100本)の記事制作ができる体制を目指しましょう。
内部:ディレクター兼編集者:1名
外部:ライター:5〜10名
▲業務委託との役割分担社内では、コンテンツの立案や編集、品質管理といった業務を担当し、取材や執筆、撮影といった制作の実務は業務委託に依頼しましょう。
理想的な業務委託併用型の体制
理想的な業務委託併用型の体制構築として、弊社(株式会社GIG)の体制を紹介します。弊社では以下の体制を組み、月間約150本の記事を制作。
内部:
ディレクター兼編集者:6名
ライター:6名
デザイナー:1名外部:
ライター:50~60名
外部のライターの中には、一人で月10本担当する方もいれば月3本程度の方もいるなど、スキルや勤務形態によって様々です。
社内完結型の内製化を進める方法
社内完結型の内製化を進める場合は、記事制作費を支給するインセンティブ制度を設けるのがおすすめです。特にエンジニアやデザイナーなど普段記事制作に携わらない人に制作を依頼する場合、本人にメリットがないと断られるケースも。
弊社(株式会社GIG)もインセンティブ制度を設けており、エンジニアやデザイナーなど多くの社員が以下のような社内ブログを執筆しています。
▲弊社社員が執筆した記事また、誰でも記事執筆ができるように、構成案や執筆例を用意しておくことで、制作のハードルを下げられるでしょう。
まとめ
記事制作の内製化は、全てを社内で実施する方法だけではありません。
まずは業務委託のライターやデザイナーなどと協力し、不足しているリソースやスキルを補う業務委託併用型がおすすめです。
一方で、顧客の興味関心を惹きつけたい場合や社内の人しか知らないエピソードをコンテンツ化したい場合は、社内完結型の内製化を目指しましょう。その際、記事制作費を支給したり、構成案を用意したりするとスムーズに内製化できます。
コンテンツマーケティングの総合パートナーの「コンマルク」では、内製化支援サービスを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。
- インタビュー記事制作 / 設計
- SEOコンテンツ制作 / 設計
- ホワイトペーパー制作 / 設計
- 動画制作 / 設計
- アクセス解析基盤設計
- アクセス解析・Webコンサルティング
- Web広告・SNS広告
- コンセプト / ペルソナ / CJM設計
- コンテンツマーケティング伴走支援 など

ファッション・ライフスタイルにまつわるWebメディアの編集者として、学生時代より記事制作にまつわる業務を広く経験したのち、2023年にGIGへジョイン。 前職では年間約500本の記事をディレクションし、現在は業種を問わずさまざまなお客様の取材コンテンツ制作(年間約120本)、ホワイトペーパー制作、SEO設計などを行う。