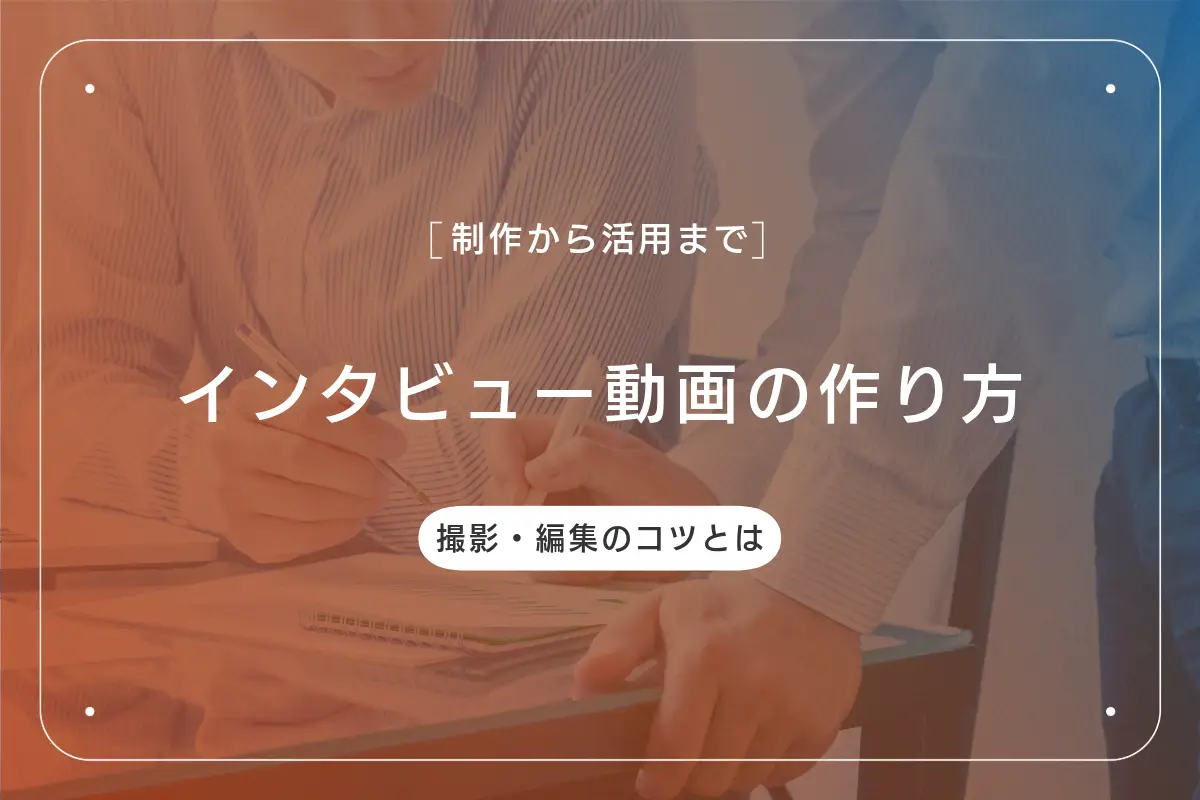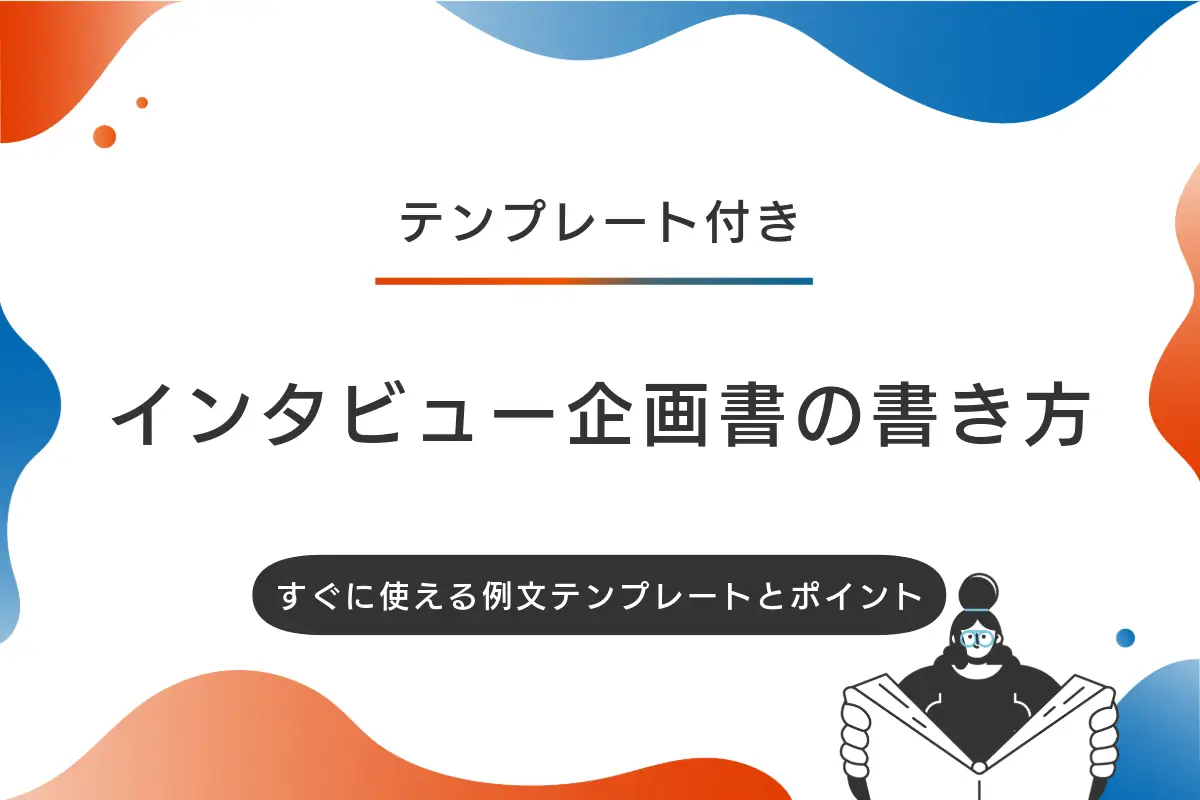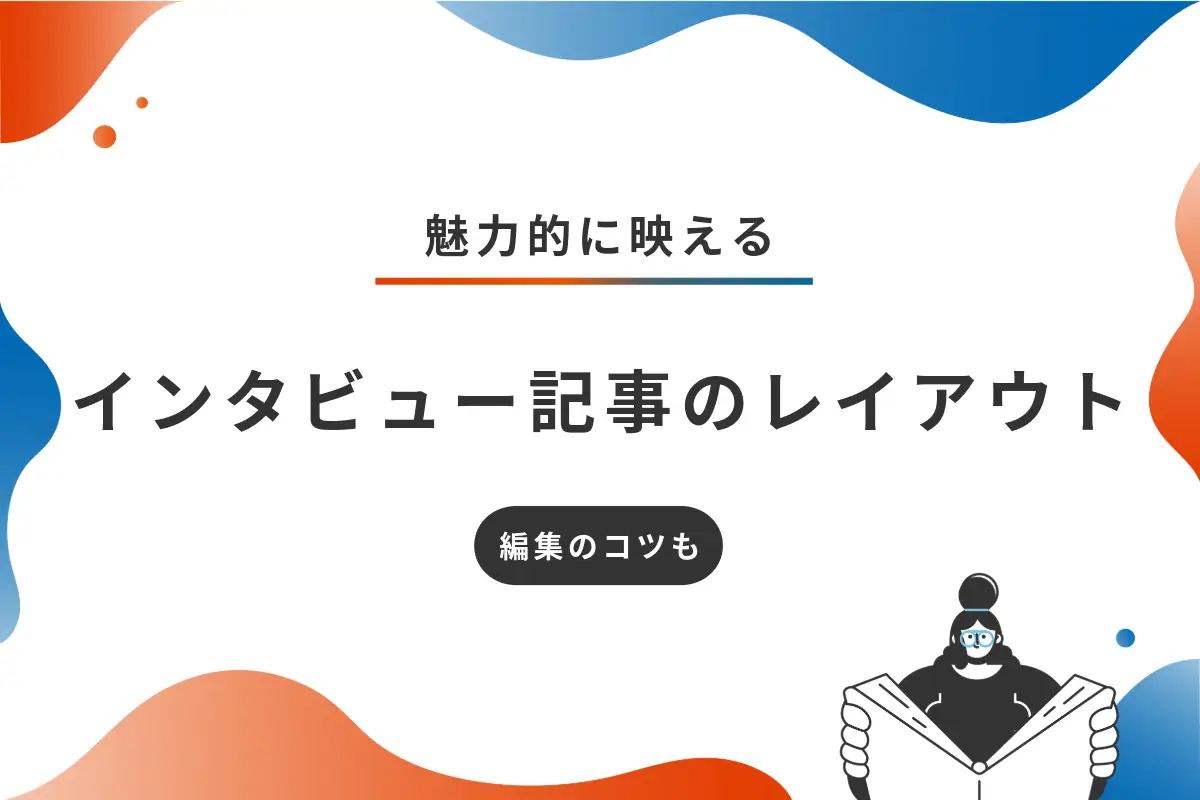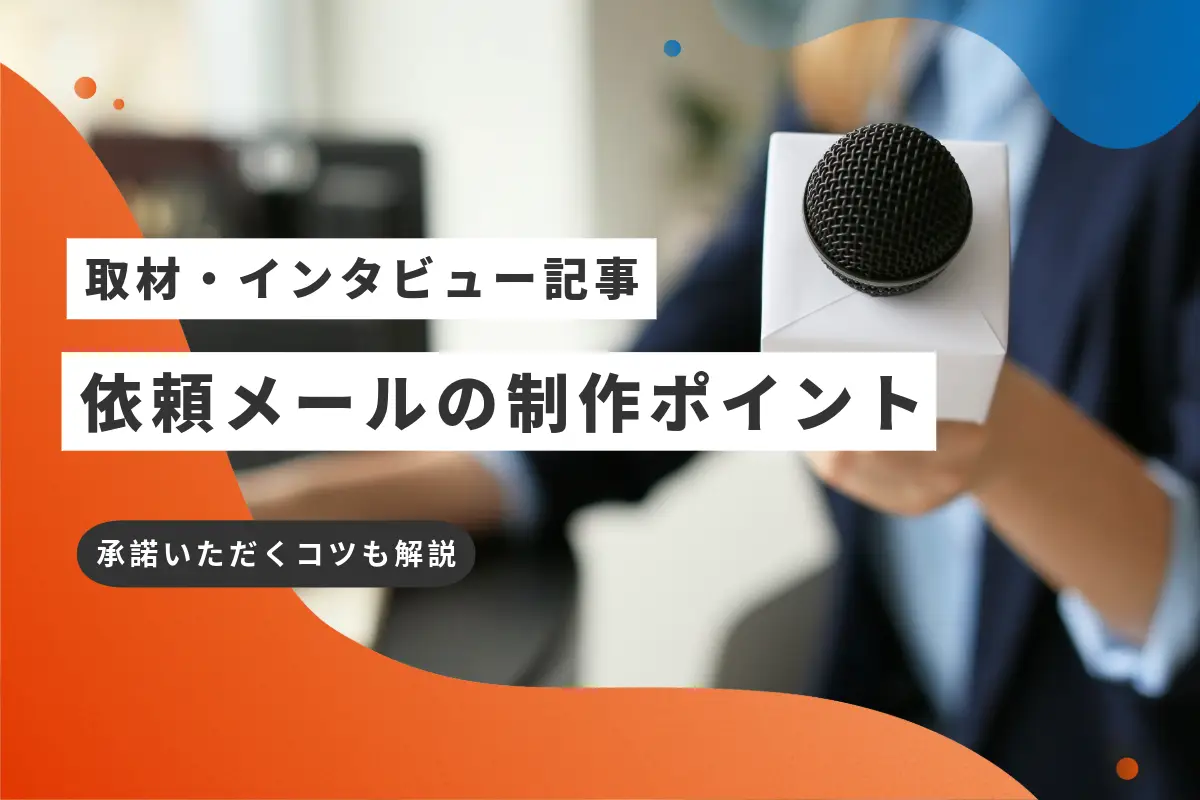社内報のコンテンツ企画のコツ!定番ネタや読まれる記事を作るポイントも解説

社内報は企業と従業員をつなぐコミュニケーションツールですが、毎号魅力的なコンテンツを企画し続けることは簡単ではありません。
本記事では、読まれる社内報コンテンツを企画するためのコツを解説します。企画立案の基本的な考え方やネタ探しのテクニックについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
社内報コンテンツ企画の基本
社内報が読まれない原因の一つは、コンテンツの軸が曖昧であることです。ここでは、社内報のコンテンツ企画で押さえるべき3つの軸について解説します。
読者が本当に知りたい情報を見極める
社内報の読者である従業員が本当に知りたい情報は何でしょうか。経営層が伝えたい情報と、従業員が読みたい情報にはギャップが存在することが多く、このギャップを埋めることが企画の第一歩となります。
定期的なアンケート調査やヒアリングを実施し、読者の関心事を把握しましょう。例えば新入社員は先輩社員の仕事ぶりや社内制度に関心が高く、中堅社員はキャリア形成や他部署の動向に興味を持つ傾向があります。
読者層ごとのニーズを整理し、各号でバランスよくコンテンツを配分することで、幅広い層に読まれる社内報を作ることができます。
自社の文化に合ったトーンで企画する
社内報は企業文化を反映する鏡のような存在です。革新的な企業文化を持つ会社では斬新な企画が歓迎される一方、伝統を重んじる企業では堅実な内容が求められます。
そのため社内報の制作では自社の企業文化を正しく理解し、それに合致したトーンやスタイルでコンテンツを企画することがポイントです。
ただし、保守的な企業でも少しずつ新しい要素を取り入れることで、社内報を通じて企業文化の変革を促すこともできます。企業理念やビジョンを具現化するようなコンテンツを意識的に組み込むことで、社内報を通した組織文化の醸成を実現できるでしょう。
定番コーナーと新企画を上手に組み合わせる
読者に安心感を与える定番コーナーと、新鮮さを提供する新企画のバランスをとることが、飽きられない社内報作りの鍵となります。
例えば社長メッセージ、新入社員紹介、部署紹介などは定番コーナーの一例です。これらは読者が期待している情報であり、継続することで社内報への信頼感を醸成します。
一方で、季節ごとの特集や時事ネタを取り入れた企画、社員参加型のコンテンツなど、変化を持たせる要素も必要です。新規性のある企画を全体の3割程度組み込むことで、マンネリ化を防ぐことができます。
読まれる社内報を生み出すコンテンツ企画のコツ
社内報コンテンツ企画の基本軸を押さえたら、次は読まれる社内報を作るための具体的なコツについてみていきましょう。
ストーリー性を重視する
社内報では、単なる情報の羅列ではなく、読み物として楽しめるストーリー性のある記事を心がけましょう。例えば新商品開発の紹介では、開発秘話や苦労話、開発者の想いなどを交えることで、社員の共感を呼ぶコンテンツになります。
数字やデータを紹介する際も、その背景にある人間ドラマを描くことで、無味乾燥な報告から生き生きとした読み物へと変わります。またプロジェクトの成功事例では、困難を乗り越えたエピソードを具体的に描写することが効果的です。
ビジュアル要素を活用する
文字ばかりの社内報は読む気が起きません。写真、イラスト、図表、インフォグラフィックスなど、ビジュアル要素を活用して視覚的に訴求力のあるコンテンツを作りましょう。
例えば社員の写真は、記事に親しみやすさを加えます。データや統計はグラフ化し、複雑な業務フローは図解することで読みやすさをアップできます。
読者が参加できる企画を取り入れる
一方通行の情報発信ではなく、読者参加型のコンテンツを企画することで、社内報への関与度を高めることができます。
社員アンケートの結果発表、川柳や写真コンテスト、クイズコーナーなど、読者が参加できる企画を定期的に実施しましょう。社員の投稿を掲載することで、「自分も載るかもしれない」という期待感を生み出せます。
旬な話題をタイミングよく取り上げる
社内報の発行時期と連動した旬な話題を取り上げることで、読者の関心を引きやすくなります。
新年度には新入社員特集や組織変更の解説、夏季には熱中症対策やクールビズ特集、年末には一年の振り返りや来年の展望など、季節感のある企画を組み込みましょう。
社内のイベントや節目に合わせた特集も効果的です。創立記念日、新商品発売、新拠点開設など、タイムリーな話題を逃さずキャッチすることが大切です。
読者層を絞る
すべての従業員に等しく訴求しようとすると、結果的に誰にも響かないコンテンツになってしまいます。各記事のターゲット読者を絞り、その層に特化した内容を企画しましょう。
例えば、若手社員向けにはキャリア形成のヒントや先輩社員の体験談、管理職向けにはマネジメントのコツや他部署の取り組み事例、シニア層向けには健康管理や定年後のライフプランなど、読者層に応じた企画を展開するといった具合です。
全体のバランスを考慮しながら、各号で異なるターゲット層にフォーカスした記事を組み合わせることで、幅広い読者のニーズに応えることができます。
外部の視点を取り入れる
社内の視点だけでは気づかない新しい切り口や企画アイデアを得るために、外部の専門家やコンサルタントの意見を聞くことも有効です。
他社の成功事例や業界のトレンドを踏まえた提案は、自社の社内報をブラッシュアップする貴重なヒントとなります。時には外部ライターに取材や執筆を依頼することで、客観的で新鮮な視点の記事を掲載できるでしょう。
社外の関係者(取引先、顧客、地域住民など)へのインタビュー企画も、従業員に新たな気づきを与えるコンテンツとなります。
効果測定と改善を繰り返す
社内報の質を継続的に向上させるには、効果測定と改善を繰り返す作業が不可欠です。
Web媒体の場合、各記事の閲覧数や読了率、アンケートでの評価などのデータを収集し、どのような企画が読者に支持されているかを分析しましょう。人気記事の要因を深掘りし、不人気記事の改善点を見つけることで、より効果的な企画立案が可能になります。
定期的な編集会議で振り返りを行い、成功事例や失敗事例は編集チームで共有することで、スキルアップにもつながります。
社内報の5つの定番ネタとマンネリ化を防ぐ工夫
社内報には定番として外せないカテゴリーがある一方で、マンネリ化を防ぐための工夫も欠かせません。ここでは、定番ネタでも飽きずに読んでもらえるような工夫を紹介します。
経営・ビジョン系コンテンツ
経営層からのメッセージは社内報の核となるコンテンツですが、形式的な挨拶文では社員の心に響きません。経営者の人間的な側面を見せる工夫が必要です。
社長の一日密着取材、役員同士の対談企画、経営陣への質問コーナーなど、親しみやすさを演出する企画を取り入れましょう。中期経営計画の解説では、難しい経営用語を避け、具体的な事例やイメージ図を使って分かりやすく伝えることが大切です。
また企業理念を現場の活動と結びつける事例紹介や、ビジョン実現に向けた各部署の取り組みレポートなど、抽象的な概念を具体化する企画も効果的です。
人物・組織紹介系コンテンツ
社員紹介は定番中の定番ですが、切り口を工夫することで毎回新鮮な印象を与えることが可能です。
新入社員紹介では、入社前後のギャップや驚いたエピソード、将来の夢などを盛り込むことで、読み物として楽しめる内容になります。一方ベテラン社員の紹介では、これまでのキャリアの転機や後輩へのメッセージなど、経験の深さを感じさせる内容が適しています。
また部署紹介では、他部署との連携事例や苦労話、専門用語の解説コーナーなどを組み合わせることで、組織理解を深める良質なコンテンツとなります。プロジェクトチームの紹介では、メンバーの役割分担や、チームワークの秘訣などを具体的に描写しましょう。
業務・ナレッジ系コンテンツ
業務に関する情報は、ともすれば堅苦しい内容になりがちですが、実用性の高い情報として人気を集めることも可能です。
仕事の効率化テクニック、便利なツールの活用法、他部署も参考になる改善事例など、すぐに実践できる内容を分かりやすく紹介しましょう。失敗事例から学ぶ教訓や、トラブル対応の体験談なども、リアリティがあって読者の関心を引きます。
専門知識のシェアでは、図解やフローチャートを多用し、初心者でも理解できるレベルに噛み砕いて説明することが大切です。用語集や基礎知識コーナーを設けることで、新人教育にも活用できる資料となります。
季節・イベント系コンテンツ
季節感のある企画は、社内報に変化とリズムを与えます。単なる季節の挨拶に終わらせず、業務や社員生活と結びつけた実用的な内容にすることがポイントです。
春は新年度特集として組織変更の解説や新入社員へのアドバイス、夏は熱中症対策や省エネの取り組み、秋は下期の目標設定やスキルアップ特集、冬は一年の振り返りや健康管理など、季節に応じた切り口で企画を展開しましょう。
社内イベントのレポートでは、単なる実施報告ではなく、準備の裏話や参加者の感想、次回への改善提案なども盛り込むことで、より読み応えのある記事になります。
ネタ切れを防ぐ!社内報コンテンツの発掘方法
継続的に発行される社内報において、最大の課題は企画ネタの枯渇です。しかし、視点を変えれば社内外には無限のネタが存在しています。
ここでは、社内報コンテンツの発掘方法について紹介します。
社内の情報源を活用する
企画のネタは社内のあらゆる場所に転がっています。
営業部門の成功事例、開発部門の新技術、管理部門の業務改善など、各部署で当たり前に行われていることも、他部署から見れば新鮮な情報となることがあります。部署横断的な情報収集を行い、定期的に情報交換を行いましょう。
また社員食堂での雑談、エレベーターでの立ち話、休憩室での会話なども、貴重な情報源です。アンテナを高く張り、日常の中から企画の種を見つける習慣を身につけることが大切です。
読者の声から新しい企画を生み出す
社内報の最大の情報源は、読者である従業員自身です。定期的なアンケートやフィードバックの収集を通じて、読者が本当に求めているコンテンツを把握しましょう。
アンケートには「もっと知りたい部署」「話を聞いてみたい先輩」「解決してほしい疑問」など、具体的な要望を聞き出す質問項目を設計することがポイントです。採用された企画は提案者の名前とともに掲載することで、さらなる投稿を促すことができます。
またWeb社内報であれば、記事ごとのアクセス数や滞在時間のデータから、人気コンテンツの傾向を分析することも可能です。
外部トレンドからヒントを得る
社会的なトレンドや他社の取り組みからも、自社の社内報に活かせるアイデアを得ることができます。
働き方改革、SDGs、DX推進など、時代のキーワードを自社の取り組みと結びつけることで、タイムリーで意義のある企画が生まれます。業界紙や専門誌、ビジネス書などから得た知識を、自社の文脈に落とし込んで企画化しましょう。
SNSでの話題や、若者の間で流行しているコンテンツ形式なども参考になります。ただし、単なる模倣ではなく、自社の文化や読者層に合わせたアレンジが必要です。
社内報のコンテンツ企画ならコンマルクにご相談を
社内報は単なる情報伝達ツールではなく、組織文化を醸成し、従業員エンゲージメントを高めるメディアです。その可能性を最大限に引き出すために、自社ならではの魅力的な社内報づくりに挑戦していきましょう。
企画力を磨くことは一朝一夕にはいきませんが、読者の反応を真摯に受け止め、常に新しいアイデアにチャレンジする姿勢を持ち続けることが大切です。時には外部の専門家の力を借りることも、社内報の質を高める有効な手段となります。
株式会社GIGが提供する「コンマルク」は、年間4,000件の法人リード創出実績を持つコンテンツマーケティングサービスです。主に外部向けコンテンツ制作で培った豊富な取材・編集ノウハウは、社内報制作にも応用可能です。
【コンマルクが社内報制作でお役に立てること】
プロの取材技術で社員の本音を引き出す
読まれる記事の構成・ライティングノウハウを提供
他社事例から学んだ企画アイデアをご提案
編集者育成支援で社内の制作体制を強化
特に、数多くの企業取材を通じて蓄積した「人を魅力的に見せる」技術や、「難しい内容を分かりやすく伝える」編集力は、社内報のクオリティ向上に直結します。
社内報の企画・制作でお悩みの際は、ぜひ一度コンマルクにご相談ください。
お問い合わせはこちらから
- インタビュー記事制作 / 設計
- SEOコンテンツ制作 / 設計
- ホワイトペーパー制作 / 設計
- 動画制作 / 設計
- アクセス解析基盤設計
- アクセス解析・Webコンサルティング
- Web広告・SNS広告
- コンセプト / ペルソナ / CJM設計
- コンテンツマーケティング伴走支援 など

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。