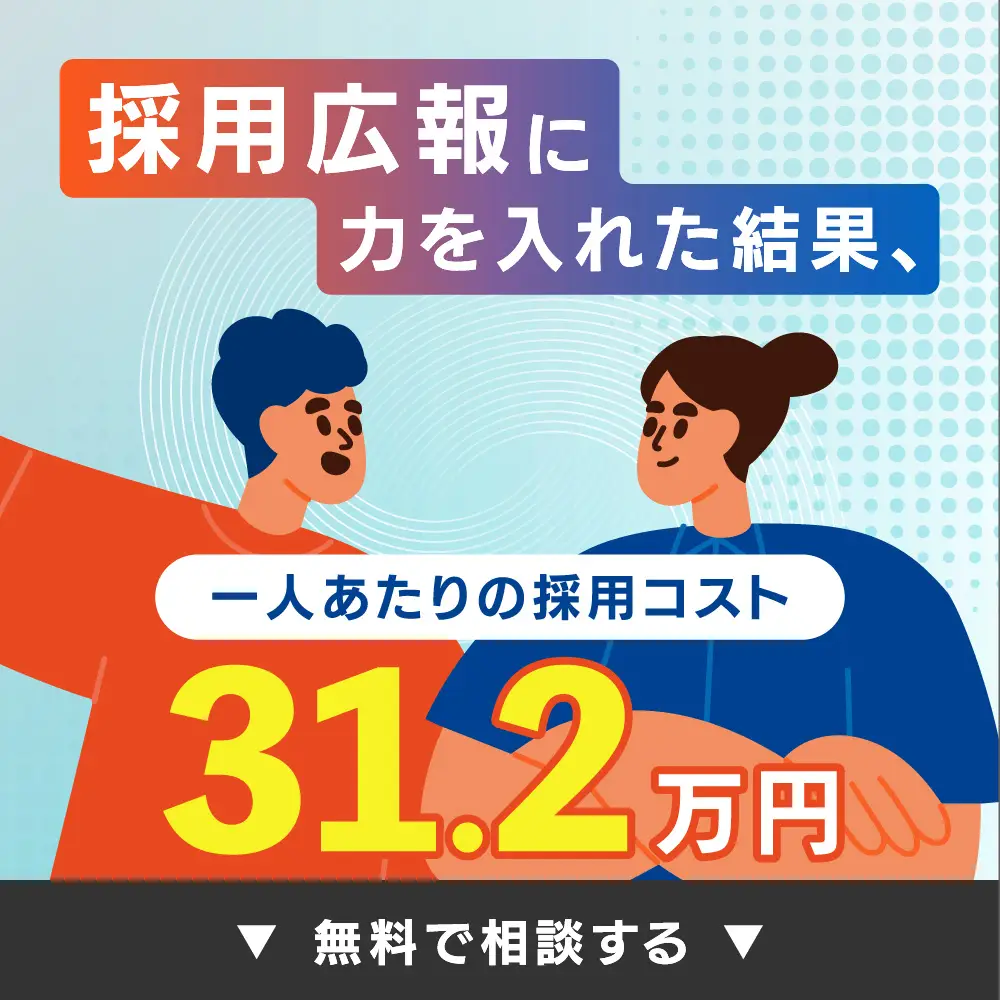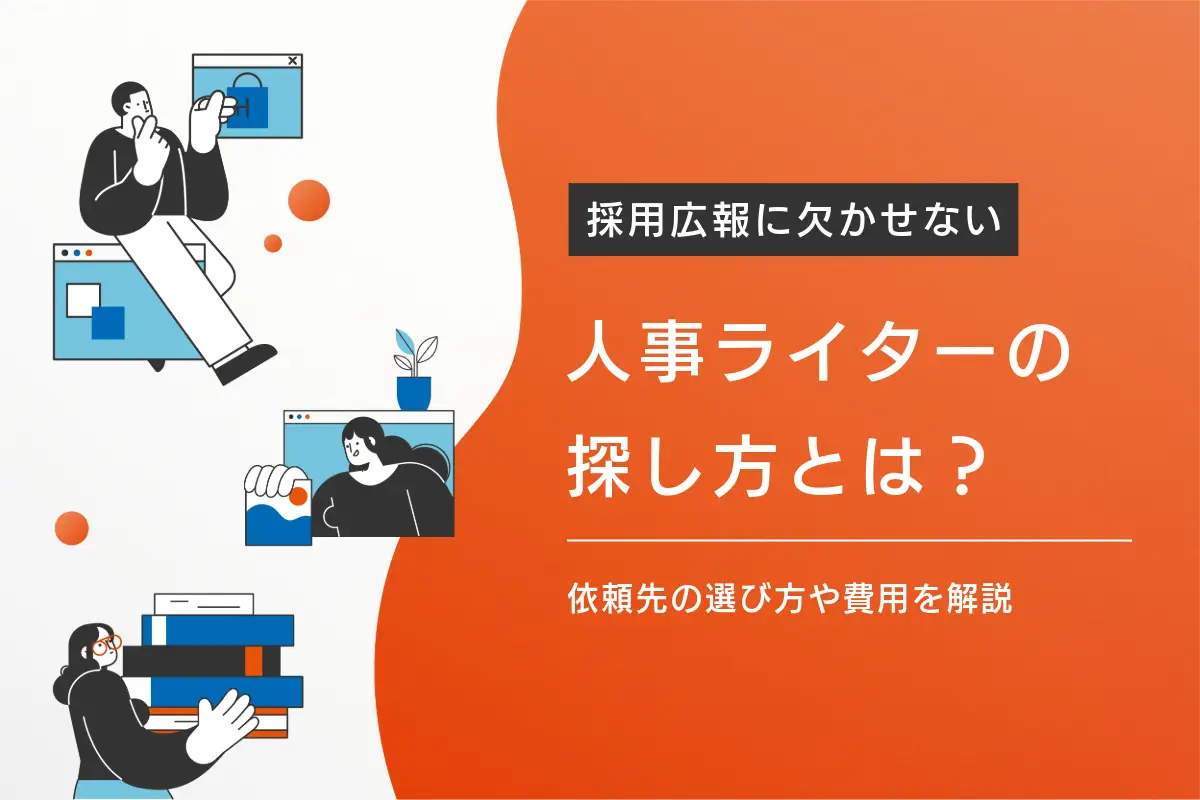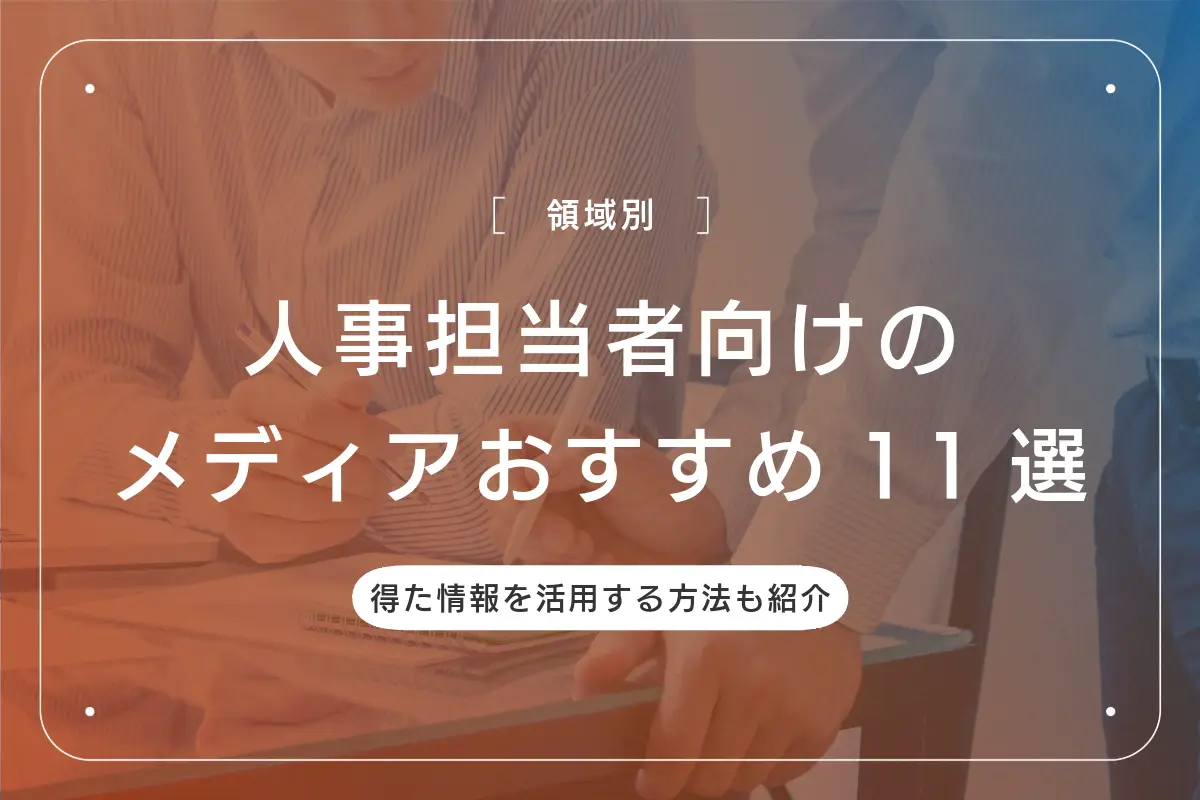オープン社内報の人気コンテンツとは? 読まれるネタの具体例と企業事例を解説

近年、社内報を社外にも公開する「オープン社内報」に取り組む企業が増加しています。しかし、いざ始めようとすると「どんなコンテンツ(ネタ)を発信すればよいか」と悩む担当者の方も多いかもしれません。
この記事では、オープン社内報で読まれる人気のコンテンツ例や、参考になる企業事例、そして運営のポイントについて詳しく解説します。
オープン社内報とは?
オープン社内報とは、従来は社員向けに限定して発行されていた社内報を、インターネットを通じて社外の誰でも閲覧できるように公開する取り組みです。noteやYouTube、自社Webサイトなどのプラットフォームを活用し、企業の日常や社員の様子を発信します。
通常の社内報が社内コミュニケーションの活性化を主な目的とするのに対し、オープン社内報は採用広報やブランディングといった社外への効果も期待できます。企業の「ありのままの姿」や「働く人々の雰囲気」をリアルに伝えることで、求職者への強力なアピールとなり採用活動に貢献したり、顧客や取引先への透明性を示すことで企業ブランディングや信頼性向上につながったりするなど、多様な目的で導入が進んでいるのです。
オープン社内報のコンテンツ例
オープン社内報の成果は、コンテンツの魅力にかかっています。ここでは、人気を集めやすいコンテンツの具体例をジャンルごとに紹介します。
会社の「人」や「文化」を伝えるコンテンツ
企業の「素顔」が最も伝わるのが、「人」にフォーカスしたコンテンツです。
スペックやデータだけでは伝わらないリアルな社風や、実際に働く人々の雰囲気を社外(特に求職者)に示すことができるため、採用時のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。また、社内的にも他部署の社員や業務への理解が深まり、コミュニケーションの活性化につながります。
■コンテンツ例
|
事業やサービス、取り組みを伝えるコンテンツ
社の事業内容やサービスについて、単なる機能紹介にとどまらず、その裏側にあるストーリーや携わる人の想いを伝えるコンテンツも有効です。新商品が生まれるまでの開発秘話や担当者の苦労、こだわりを発信することで、読者の共感を呼び、サービスへの理解と信頼を深める効果があります。
また、企業の専門性や社会的な姿勢をアピールすることは、企業ブランディングの向上に直結します。
■コンテンツ例
|
経営陣の「想い」や「ビジョン」を伝えるコンテンツ
企業の方向性や価値観を社内外に示す上で、経営陣からのメッセージは欠かせません。
トップが自らの言葉で会社のビジョンやミッション、事業への想いを語ることで、企業の進むべき道を強く印象付けられます。これは、社員のエンゲージメントを高めると同時に、社外のステークホルダー(顧客、取引先、求職者)からの信頼と共感を得るために重要です。
さらに経営陣のパーソナルな側面を見せる企画は、親近感の醸成にも役立ちます。
■コンテンツ例
|
オープン社内報の企業事例
実際にオープン社内報を運営している企業は、どのようなコンテンツを発信し、成果につなげているのでしょうか。ここでは、プラットフォームの活用方法やコンテンツの特色が異なる3社の事例を紹介します。
事例1:note株式会社
自社プラットフォーム「note」を活用し、「オープン社内報」のマガジンを運営しています。最大の特徴は、社員紹介コンテンツの豊富さです。「#noteの社員」というハッシュタグで、多様な職種の社員がどのような想いで働いているか、どのようなキャリアを歩んできたかを深く掘り下げています。
また、社内イベントのレポートや、「シャッフルランチ」のような社内コミュニケーション施策の紹介、デザイン変更の裏側、AI活用術など、業務に直結する内容からカルチャーを伝えるものまで、幅広いテーマの記事が発信されています。自社プラットフォームの活用例としても参考になる事例です。
事例2:グリー株式会社
オウンドメディア「GREE Engineering」や「GREE News」などを通じて、社内外に情報を発信しています。
エンジニア向けの技術情報発信に加えて、社内報的なコンテンツもオープンにしています。 特に、社員インタビューやプロジェクト紹介、社内イベントのレポートなどが充実しており、働く環境や企業文化を具体的に伝えています。
事例3:エン株式会社
「note」での発信に加え、YouTubeを活用した動画でのオープン社内報にも力を入れています。テキストメディアとは異なり、動画ならではのリアルな温度感や社員の表情が伝わりやすいのが強みです。
社員インタビューや座談会、オフィスツアー、社内イベントの様子などを動画コンテンツとして配信し、特に若い世代の求職者に対して効果的なアピールを行っています。テキストと動画、それぞれのメディアの特性を活かしながら、オープンな情報発信を多角的に展開している好事例といえます。
読まれるオープン社内報の作り方・運営のポイント
オープン社内報を成功させるためには、単に情報を公開するだけでなく、戦略的な視点が必要です。ここでは、読者に届き、継続的に運営していくための重要なポイントを解説します。
目的とターゲットを明確にする
まずは「何のためにオープン社内報をやるのか」という目的を明確にすることがスタートラインです。
「採用応募者を増やしたい」「企業ブランディングを強化したい」「社員のエンゲージメントを高めたい」など、目的によって発信するべきコンテンツやトーン&マナーは変わってきます。 同時に、「誰に」届けたいのかというメインターゲット(ペルソナ)も具体的に設定しましょう。
例えば、ターゲットが「新卒の求職者」なのか、「中途採用の即戦力エンジニア」なのかによって、響くコンテンツの切り口やテーマは異なります。目的とターゲットを明確にすることが、ブレない運営の基盤となります。
適切なプラットフォームを選ぶ
目的とターゲットに合わせて、発信する「場所」を選ぶことも重要です。
手軽に始めやすく、多くの読者に届く可能性がある「note」は人気の選択肢です。デザインの自由度や独自性を高めたい場合は、自社でオウンドメディア(ブログ)を構築する方法もあります。
また、動画コンテンツを中心に発信したい場合はYouTubeが適しています。最近では、より手軽な情報発信としてX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを活用する企業も増えています。それぞれのプラットフォームの特性を理解し、自社のリソースや発信内容に合ったものを選びましょう。
社内の巻き込みと継続体制を構築する
オープン社内報は、担当者だけでは成り立ちません。魅力的なコンテンツを生み出し続けるためには、現場で働く社員の協力が不可欠です。
社員インタビューや部署紹介、イベントレポートなど、多くの企画は他部署の協力なしには実現しません。 日頃から社内各所と良好な関係を築き、オープン社内報の目的や意義を共有し、協力をお願いしやすい雰囲気を作っておくことが大切です。
また、属人化を防ぎ、継続的に運営していくための体制構築も重要です。編集会議の定例化や、ネタ出しの仕組みづくり、無理のない更新頻度の設定など、長期的な視点で運営フローを整備しましょう。
効果測定と改善を行う
発信して終わりではなく、定期的に効果測定を行い、コンテンツの改善につなげるプロセスが成長の鍵となります。
Webメディアであれば、記事ごとの閲覧数(PV)や読了率、SNSでのシェア数、流入経路などを分析します。 どの記事がよく読まれているのか、どのようなテーマがターゲットに響いているのかをデータで把握しましょう。
また、記事に対する社外からのコメントや、社内アンケートなどで社員からのフィードバックを集めることも有効です。「採用面接で記事を読んだと言われた」といった定性的な成果も重要な指標となります。データを基に、企画や切り口を改善していくサイクルを回しましょう。
オープン社内報の制作・運営ならコンマルクにご相談を
オープン社内報は、従来の社内報の枠を超え、採用広報、企業ブランディング、インナーコミュニケーションの強化など、多岐にわたる効果が期待できる強力なツールです。
しかし、いざオープン社内報を始めようとすると、企画立案やインタビュー取材、継続的な運営体制の構築など、多くの課題に直面します。そんな時は、プロのサポートを活用することで、質の高いコンテンツを効率的に制作・発信できます。
株式会社GIGが提供する「コンマルク」は、年間4,000件の法人リード創出実績を持つコンテンツマーケティングサービスです。豊富な取材・編集経験を活かし、オープン社内報の制作・運営をサポートします。
社員インタビューや座談会の企画・取材・執筆
企業文化が伝わる魅力的なストーリー設計
SEOを意識した読まれる記事構成
継続運営のための編集体制構築支援
社内スタッフへの編集スキル育成研修
オープン社内報の立ち上げや改善をお考えの企業様は、ぜひコンマルクにご相談ください。
よくある質問
オープン社内報と通常の社内報の違いは何ですか?
通常の社内報は社員のみが閲覧できる社内限定の情報発信ですが、オープン社内報はインターネットを通じて社外の誰でも閲覧できます。目的も異なり、通常の社内報が社内コミュニケーション活性化を主目的とするのに対し、オープン社内報は採用広報や企業ブランディングなど社外への効果も狙います。
オープン社内報の運営にかかる費用はどれくらいですか?
noteなどの無料プラットフォームを使えば初期費用はかかりません。自社サイトで運営する場合はサイト構築費が必要です。外部委託する場合は、記事制作が1本3〜10万円、運営代行は月額10〜30万円程度が相場です。社内で運営する場合も、担当者の人件費と協力社員の工数を考慮する必要があります。
どのようなコンテンツから始めればよいですか?
まずは社員インタビューや新入社員紹介など「人」にフォーカスしたコンテンツがおすすめです。比較的制作しやすく、読者の関心も高い傾向があります。次に社内イベントレポートや部署紹介など、企業文化が伝わるコンテンツを追加していきます。慣れてきたら経営陣メッセージや事業開発秘話など、より深い内容にチャレンジするとよいでしょう。
情報公開のリスクはどう管理すればよいですか?
機密情報や個人情報の流出防止のため、公開前の承認フローを確立することが必須です。社員の顔写真や実名掲載は本人同意を得て、プライバシーポリシーを明確にします。また、競合他社に戦略が伝わらないよう、公開する情報のレベルを事前に定めておきます。炎上リスクに備え、SNSガイドラインの策定と、問題発生時の対応体制も整備しておくことが重要です。
- 採用ブログ・オウンドメディア運用代行
- Wantedly運用代行コンサルティング
- 採用動画制作
- 採用サイト・コンテンツ制作

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。