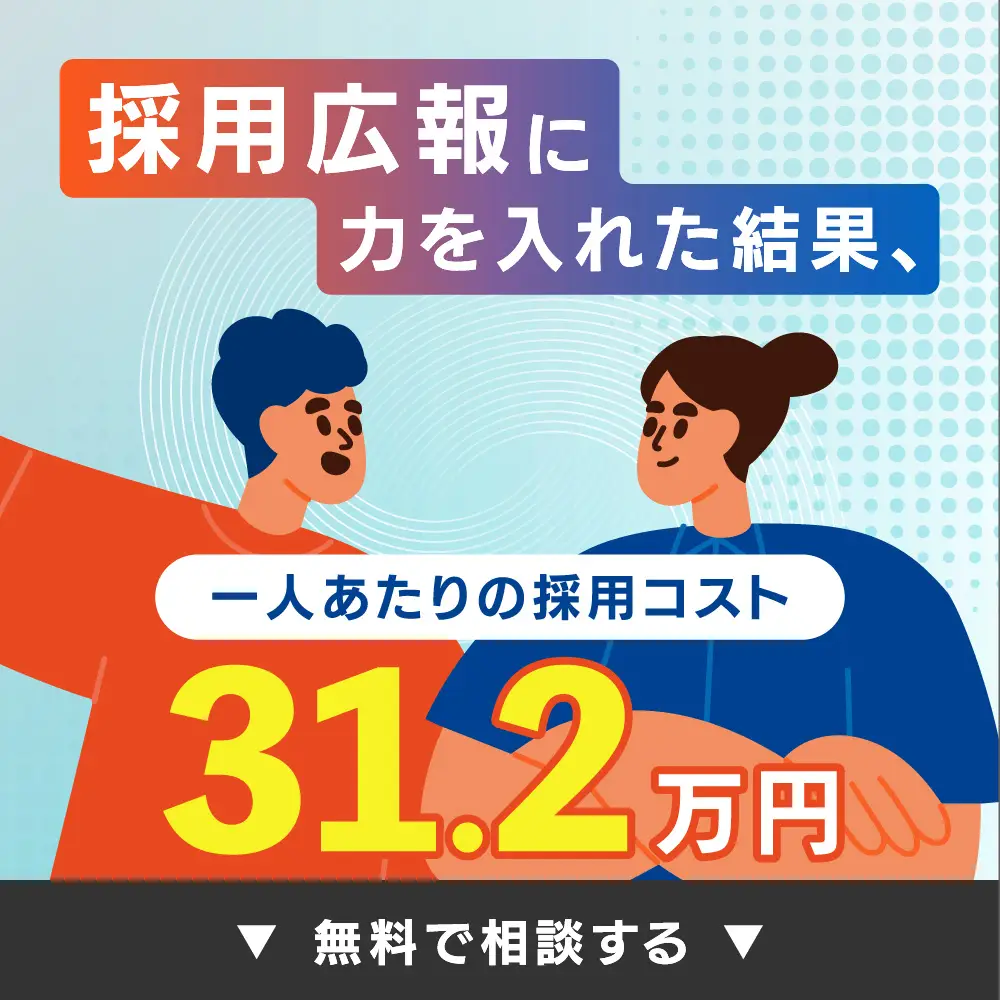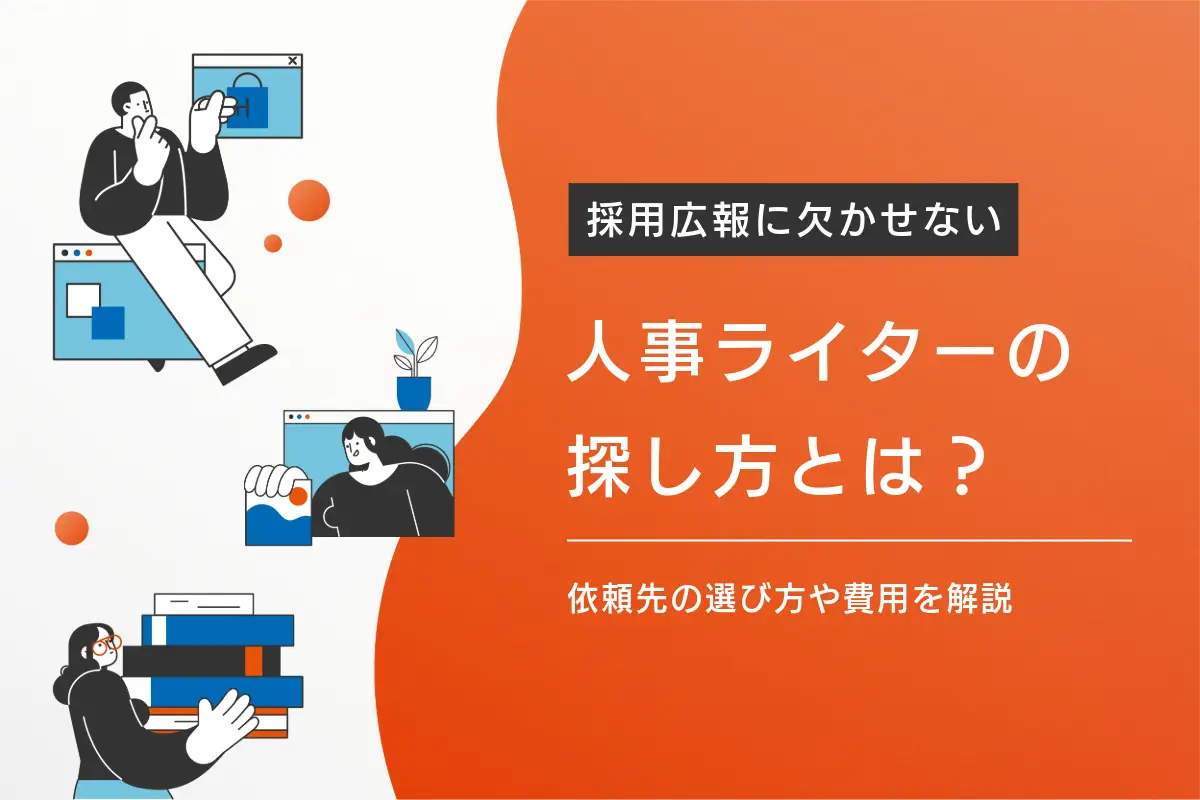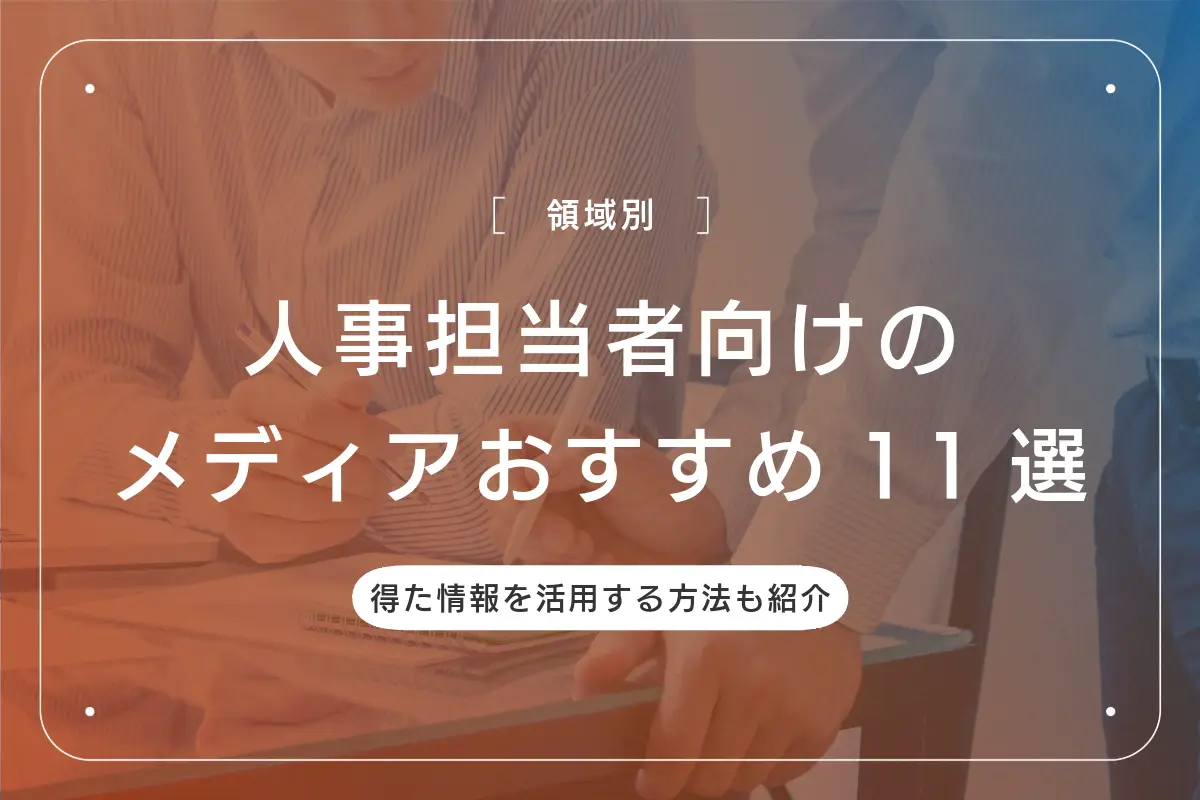採用コンセプトとは?メリットや作り方・5社の企業事例も紹介

採用活動において「なぜ優秀な人材が集まらないのか」「内定辞退が多い」といった悩みを抱えていませんか。このような課題の根本には、採用コンセプトの不在や曖昧さが潜んでいることが少なくありません。
この記事では、採用コンセプトの基本的な考え方から具体的な作り方、成功企業の事例を紹介します。自社の採用活動を根本から見直したい人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:採用サイトとは?効果や作り方、成功のコツを事例とともに紹介
関連記事:採用サイトに必要なコンテンツ|特徴や制作のポイントを紹介
採用コンセプトとは
採用コンセプトとは、企業が採用活動を行う上での基本的な方針や、求める人物像、大切にしている価値観などを一言で表現したものです。採用活動における「北極星」のような存在であり、すべての採用施策の判断基準となります。
関連記事:コンセプトの考え方を解説!意味や重要性、設計の流れも紹介
例えば、サントリーホールディングスの「やってみなはれ」や、伊藤忠商事の「ひとりの商人、無数の使命」といったメッセージは、単なるキャッチフレーズではありません。これらは企業の本質的な価値観を凝縮し、求職者に対して「どのような人材を求めているか」「どのような環境で働けるか」を端的に伝える採用コンセプトなのです。
関連記事:テーマとコンセプトの違いをわかりやすく解説!決め方やビジネスでの活用法を事例で紹介
なぜ今、採用コンセプトが注目されているのか
近年、採用コンセプトの重要性が高まっている背景には、採用市場の構造的な変化があります。
まず、求職者の価値観が多様化しています。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「働きがい」「成長機会」「社会的意義」など、さまざまな要素を総合的に判断して就職先を選ぶようになりました。画一的なアプローチでは、もはや優秀な人材を惹きつけることはできません。
また、情報の透明性が高まったことも大きな要因です。SNSや口コミサイトを通じて、企業の実態は容易に知れ渡るようになりました。表面的な採用メッセージと実態が乖離していれば、すぐに見破られてしまいます。だからこそ、企業の本質を表現した採用コンセプトが必要なのです。
採用コンセプトによって得られるメリット
採用コンセプトを明確に設定することで、企業の採用活動は劇的に変化します。ここでは、その具体的な効果を5つの観点から解説します。
1. 採用のミスマッチを防ぐ
採用コンセプトは、企業と求職者の相互理解を深める重要な役割を果たします。
例えば、「挑戦を恐れない、新しい価値を創造する仲間へ」という採用コンセプトを掲げた場合、安定志向の強い求職者は自然と応募を控えるでしょう。一方で、新しいことにチャレンジしたいという意欲的な人材が集まりやすくなります。
これは決して排他的な姿勢ではありません。むしろ、お互いにとって最適なマッチングを実現するための、誠実なコミュニケーションといえます。入社後のギャップによる早期離職を防ぐことは、企業にとっても求職者にとってもメリットがあるのです。
2. 採用活動の効率化につながる
明確な採用コンセプトは、採用プロセス全体の効率化に貢献します。
求める人材像が明確になることで、書類選考の基準が統一され、面接での質問項目も体系化されます。面接官による評価のばらつきも減少し、より公平で効率的な選考が可能になります。
また、採用コンセプトに基づいて採用広報を展開することで、自社にマッチした人材からの応募が増加します。結果として、選考にかかる時間とコストを大幅に削減できるのです。
3. 企業ブランディングを強化できる
採用コンセプトは、企業の独自性を際立たせる強力なブランディングツールとなります。
同業他社が似たような採用メッセージを発信する中で、独自の採用コンセプトを持つ企業は圧倒的に目立ちます。「世界を変える、変人募集」といったユニークなコンセプトは、求職者の記憶に残り、企業への興味を喚起します。
さらに、採用コンセプトは採用活動だけでなく、企業全体のブランドイメージ向上にも寄与します。「この会社は面白い人材を求めている」「革新的な企業文化がありそう」といった印象は、顧客や投資家に対してもポジティブな影響を与えるのです。
4. 社内の意識を統一できる
採用コンセプトの策定プロセスは、組織全体の価値観を再確認する機会にもなります。
「どのような人材と一緒に働きたいか」「自社の強みは何か」といった問いに向き合うことで、既存社員も自社の魅力を再発見します。これは社員のエンゲージメント向上にもつながり、結果として採用活動への協力意識も高まります。
実際、採用コンセプトを明確にした企業では、社員紹介による採用が増加する傾向があります。社員が自信を持って友人や知人に自社を勧められるようになるからです。
5. 長期的な組織成長につながる
採用コンセプトに基づいて採用された人材は、企業文化との親和性が高く、長期的に活躍する可能性が高いといえます。
価値観を共有する仲間が集まることで、組織の一体感が生まれ、イノベーションが起きやすい環境が整います。また、採用コンセプトに共感して入社した社員は、その理念を体現するロールモデルとなり、次世代の採用活動にもポジティブな影響を与えます。
このような好循環が生まれることで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
採用コンセプトと採用キャッチコピーの違い
採用コンセプトと採用キャッチコピーは混同されがちですが、それぞれ異なる役割と特徴を持っています。この違いを正しく理解することは、効果的な採用戦略を立てる上で重要です。
採用コンセプトの特徴
採用コンセプトは、採用活動全体の方向性を定める戦略的な指針です。以下のような特徴があります。
採用活動の根幹となる考え方や価値観を表現
中長期的に使用される(3〜5年程度)
社内向けの意思統一ツールとしても機能
具体的な施策を検討する際の判断基準となる
例えば、「多様性を力に変える組織づくり」という採用コンセプトは、国籍や性別、バックグラウンドの異なる人材を積極的に採用し、イノベーションを生み出すという企業の基本姿勢を示しています。
採用キャッチコピーの特徴
一方、採用キャッチコピーは、採用コンセプトを求職者に伝えるための表現手法です。
採用コンセプトを魅力的に表現したもの
求職者の注目を集めることが主目的
年度ごとに変更することも多い
印象に残りやすい短いフレーズ
先ほどの採用コンセプトを基に、「国境を越えろ、常識を超えろ」というキャッチコピーを作ることができます。これは同じ価値観を、より印象的で記憶に残る形で表現したものです。
採用コンセプトと採用キャッチコピーの使い分け方
採用コンセプトと採用キャッチコピーは、車の両輪のような関係にあります。
項目 | 採用コンセプト | 採用キャッチコピー |
目的 | 採用活動の方向性を定める | 求職者の注目を集める |
対象 | 社内関係者+求職者 | 主に求職者 |
使用期間 | 中長期(3〜5年) | 短期(1年程度) |
表現 | 具体的で説明的 | 印象的で感情に訴える |
文字数 | 20〜50文字程度 | 10〜25文字程度 |
重要なのは、採用キャッチコピーは採用コンセプトから派生するものであり、決して独立して存在するものではないということです。キャッチコピーがどれだけ魅力的でも、それが採用コンセプトと乖離していれば、求職者に混乱を与えてしまいます。
効果的な採用コンセプトの作り方6ステップ
採用コンセプトの作成は、企業の未来を左右する重要なプロセスです。ここでは、6つのステップに沿って、効果的な採用コンセプトの作り方を解説します。
ステップ1:自社分析と現状把握
採用コンセプトづくりの第一歩は、自社を深く理解することから始まります。
まず、以下の観点から自社の現状を分析しましょう。
企業理念・ビジョン・ミッション:創業の想いや目指す未来像を再確認
事業戦略:今後3〜5年でどのような事業展開を計画しているか
組織文化:社員が大切にしている価値観や行動様式
採用実績:過去に採用した人材の特徴や活躍状況
特に重要なのは、「建前」ではなく「本音」の部分を掘り下げることです。例えば、「チームワークを重視する」という表面的な言葉の裏に、「個人の成果よりもチーム全体の成功を優先できる人」という具体的な期待があるはずです。
社員インタビューも有効な手法です。「なぜこの会社を選んだのか」「どんな瞬間にやりがいを感じるか」といった質問を通じて、自社の魅力を言語化していきましょう。
ステップ2:ターゲット人材の明確化
求める人材像を具体的に描くことが、採用コンセプトの精度を高めます。
ペルソナ設計では、以下の要素を詳細に設定します。
基本属性 | 年齢、学歴、職歴、専門スキル |
価値観 | 仕事に対する考え方、キャリア観、人生観 |
行動特性 | 情報収集方法、意思決定プロセス、コミュニケーションスタイル |
志向性 | 成長意欲、安定志向、挑戦意欲のバランス |
課題・悩み | 現在の仕事や転職活動で抱えている不満や不安 |
ただし、理想を追求しすぎて非現実的なペルソナにならないよう注意が必要です。実際に活躍している社員の特徴を分析し、「こんな人なら自社で活躍できる」というリアルな人物像を描きましょう。
ステップ3:競合分析と差別化ポイントの発見
他社との違いを明確にすることで、独自性のある採用コンセプトが生まれます。
競合分析では、同業他社だけでなく、求職者が比較検討する可能性のある企業も対象に含めましょう。例えば、IT企業であれば、同じIT業界だけでなく、コンサルティングファームや金融機関も競合になり得ます。
分析のポイントは以下のとおりです。
競合企業の採用コンセプトやメッセージ
提供している価値や魅力
採用手法や選考プロセス
求職者からの評判や口コミ
重要なのは、競合を真似るのではなく、自社ならではの強みを見つけ出すことです。「大手企業のような安定性はないが、裁量権の大きさは圧倒的」「給与水準は平均的だが、働き方の柔軟性は業界トップクラス」といった、トレードオフの関係を明確にすることで、差別化ポイントが見えてきます。
ステップ4:自社の提供価値の言語化
求職者にとっての価値を、具体的かつ魅力的に表現します。
ここでは、機能的価値と情緒的価値の両面から整理することが重要です。
【機能的価値の例】
最先端技術に触れられる環境
グローバルなプロジェクトへの参画機会
充実した教育研修制度
【情緒的価値の例】
社会課題解決への貢献実感
仲間と切磋琢磨する刺激的な環境
自己実現と成長の喜び
これらの価値を整理する際は、「なぜそれが価値になるのか」まで深掘りしましょう。例えば、「フレックスタイム制」という制度そのものではなく、「家族との時間を大切にしながらキャリアを築ける」という価値として表現することで、求職者の心に響くメッセージになります。
ステップ5:コンセプトの統合とメッセージ化
これまでの分析結果を統合し、一つの力強いメッセージに結晶化させます。
効果的な採用コンセプトには、以下の要素が含まれています。
独自性:他社との明確な違い
共感性:ターゲット人材の心に響く
具体性:抽象的すぎない、イメージしやすい表現
一貫性:企業理念や事業戦略と整合している
発展性:さまざまな施策に展開できる
メッセージ化のプロセスでは、複数の案を作成し、比較検討することをお勧めします。「イノベーションを起こす挑戦者たちへ」「技術で社会を変える、未来の設計者募集」「常識を疑い、新しい答えを創る仲間へ」など、異なる切り口から表現してみましょう。
ステップ6:検証とブラッシュアップ
作成した採用コンセプトを多角的に検証し、完成度を高めます。
検証は以下の観点から行います。
社内検証 |
|
社外検証 |
|
特に重要なのは、ターゲットとなる求職者層からのフィードバックです。採用イベントやインターンシップの機会を活用し、率直な意見を収集しましょう。「このメッセージを見てどう感じるか」「どんな会社だと思うか」といった質問を通じて、意図したとおりに伝わっているかを確認します。
最終的には、これらのフィードバックを踏まえて修正を重ね、全社で自信を持って発信できる採用コンセプトに仕上げていきます。
採用コンセプトの企業事例5選
ここでは、企業の採用コンセプト事例を5つ紹介します。
1. 株式会社ニトリ「君の夢は、君を創る。」
 ▲出典:株式会社ニトリ株式会社ニトリは「君の夢は、君を創る。」という採用コンセプトで、若者の夢やキャリアに真剣に向き合う姿勢を打ち出しています。夢を持つことで未来のビジョンが明確になり、その実現に向けて成長してほしいというメッセージです。
▲出典:株式会社ニトリ株式会社ニトリは「君の夢は、君を創る。」という採用コンセプトで、若者の夢やキャリアに真剣に向き合う姿勢を打ち出しています。夢を持つことで未来のビジョンが明確になり、その実現に向けて成長してほしいというメッセージです。
個人の挑戦を後押しする自由で風通しの良い企業文化が背景にあり、主体的に行動できる人材を歓迎しています。
2. 株式会社NTTデータグループ「世界を変える、変わらぬ信念。」
 ▲出典:株式会社NTTデータグループ株式会社NTTデータグループの採用コンセプトは「世界を変える、変わらぬ信念。」です。創業以来一貫して「情報技術で新しい価値を創造し、より豊かな社会を実現する」という信念を持ち続けています。
▲出典:株式会社NTTデータグループ株式会社NTTデータグループの採用コンセプトは「世界を変える、変わらぬ信念。」です。創業以来一貫して「情報技術で新しい価値を創造し、より豊かな社会を実現する」という信念を持ち続けています。
社会課題の解決や新たな仕組みづくりに挑戦し続ける姿勢を求めており、変化の激しい時代においても揺るがない信念を持つ人材を重視しています。
3. サントリーホールディングス株式会社「やってみなはれ」
 ▲出典:サントリーホールディングス株式会社サントリーホールディングス株式会社の採用コンセプトは「やってみなはれ」。これは創業者の精神を受け継いだ言葉で、チャレンジ精神と自ら考え行動する力を重視しています。
▲出典:サントリーホールディングス株式会社サントリーホールディングス株式会社の採用コンセプトは「やってみなはれ」。これは創業者の精神を受け継いだ言葉で、チャレンジ精神と自ら考え行動する力を重視しています。
多様な価値観を受け入れ、世界を舞台に新しいことへ果敢に挑戦できる人材を歓迎。自分の意思でやり抜き、成果を出す覚悟を持つ人に活躍の場を提供しています。
4. 株式会社三井住友銀行「挑戦者よ、世界を揺らせ」
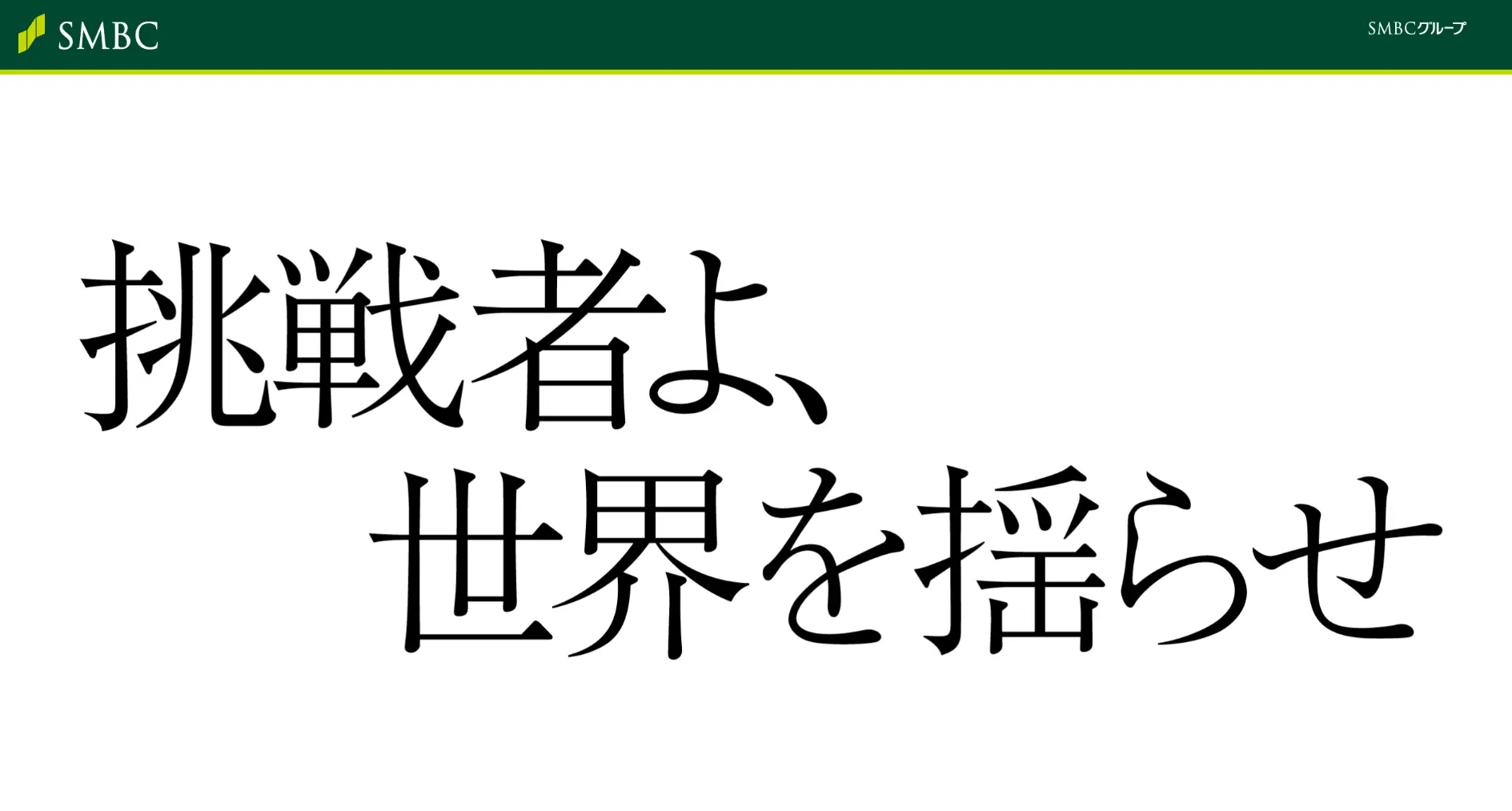 ▲出典:株式会社三井住友銀行金融業界の変革をリードし続けるという同社の姿勢を象徴するメッセージです。株式会社三井住友銀行では、伝統的な銀行業の枠を超え、時代のイノベーターであり続けるために「挑戦」を重視し、失敗を恐れず果敢に新しいことへ取り組む人材を歓迎しています。
▲出典:株式会社三井住友銀行金融業界の変革をリードし続けるという同社の姿勢を象徴するメッセージです。株式会社三井住友銀行では、伝統的な銀行業の枠を超え、時代のイノベーターであり続けるために「挑戦」を重視し、失敗を恐れず果敢に新しいことへ取り組む人材を歓迎しています。
このスローガンには、社員一人ひとりが現状に満足せず、変革意識を持って行動することで、顧客や社会、ひいては世界に大きなインパクトを与えられるという期待が込められています。
5. アクセンチュア株式会社「変化の中心で働く」
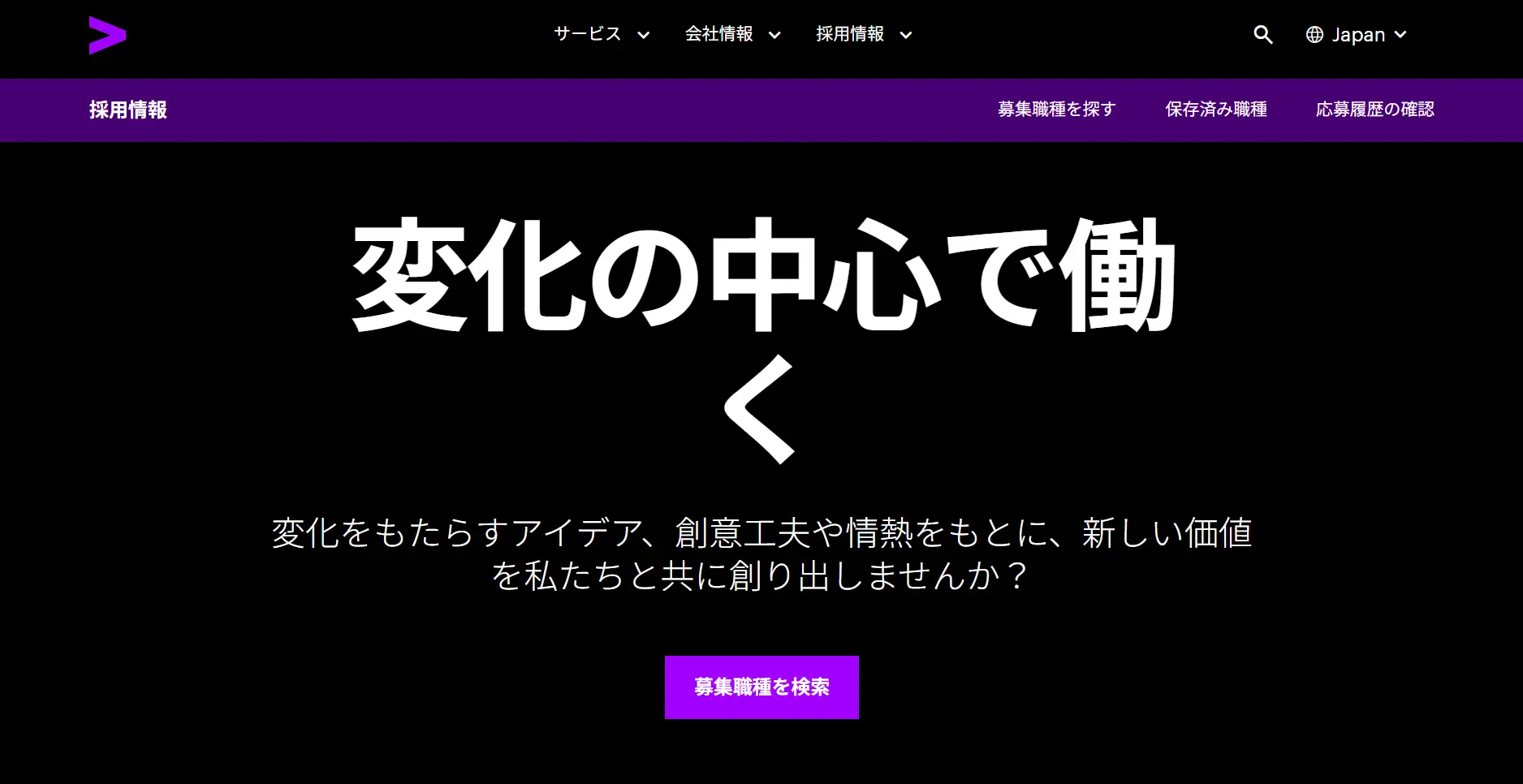 ▲出典:アクセンチュア株式会社アクセンチュア株式会社は「変化の中心で働く」という採用コンセプトを掲げています。最先端のテクノロジーを活用し、日々進化する業界の中で新たな価値を生み出すことを目指しています。
▲出典:アクセンチュア株式会社アクセンチュア株式会社は「変化の中心で働く」という採用コンセプトを掲げています。最先端のテクノロジーを活用し、日々進化する業界の中で新たな価値を生み出すことを目指しています。
変化を楽しみ、困難な状況でも前向きに挑戦できるタフな人材を求めており、グローバルな現場で成長したい人にとって魅力的な環境です。
採用コンセプト設定時のよくある失敗
優れた採用コンセプトを作るためには、陥りがちな失敗を理解し、回避することが重要です。ここでは、企業が経験した失敗事例を踏まえて、注意すべきポイントを解説します。
失敗1:理想と現実のギャップがある
最も多い失敗は、企業の実態とかけ離れた理想的なコンセプトを設定してしまうことです。
例えば、トップダウンの意思決定が中心の企業が「自由闊達な議論で新しい価値を生む」というコンセプトを掲げても、入社後のギャップに苦しむ社員を生み出すだけです。
この問題を避けるためには、以下の対策が有効です。
現場社員へのヒアリングを徹底する
退職者インタビューで本音を聞く
第三者機関による組織診断を実施する
「今すぐには実現できないが、3年後には実現したい」という将来像として位置づける
採用コンセプトは「ありのままの姿」と「目指したい姿」のバランスが重要です。現状を否定するのではなく、現状の良さを活かしながら、より良い方向へ進化させるという姿勢で設定しましょう。
失敗2:表現が抽象的すぎる
「革新的な未来を創造する」「無限の可能性に挑戦」といった抽象的な表現は、求職者の心に響きません。
このような表現の問題点は以下のとおりです。
どの企業にも当てはまる汎用的な内容
具体的なイメージが湧かない
企業の独自性が伝わらない
実際の仕事内容との関連性が不明確
抽象度を下げるテクニックとして、「5W1H」で具体化する方法があります。「誰が(Who)」「何を(What)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の観点から、コンセプトを具体的に説明できるか確認してみましょう。
失敗3:ターゲットが不明確
「すべての人に愛される企業」を目指すあまり、誰にも刺さらないコンセプトになってしまうケースがあります。
万人受けを狙った結果、特徴のない平凡なメッセージになってしまうのです。優秀な人材ほど、自分に向けられたメッセージかどうかを敏感に感じ取ります。
ターゲットを明確にする際のポイント:
「全員」ではなく「特定の価値観を持つ人」に絞る
ターゲット以外の人が違和感を持つくらいが適切
社内で活躍している人材の共通点を分析する
求める人材像を「〇〇な人」と一言で表現できるか確認する
失敗4:流行に安易に追従してしまう
「DX」「SDGs」「ダイバーシティ」など、流行のキーワードを安易に使用すると、本質が伝わりません。
これらの概念自体は重要ですが、自社の文脈で咀嚼せずに使うと、表面的な印象を与えてしまいます。求職者は「またか」と感じ、むしろ企業への興味を失ってしまう可能性があります。
流行語を使う場合の注意点:
なぜその概念が自社にとって重要なのかを説明できるか
具体的な取り組みや実績があるか
自社ならではの解釈や実践方法があるか
3年後も使い続けられる普遍性があるか
失敗5:社内コンセンサスが不足している
人事部門だけで作成し、経営層や現場の理解を得ていないコンセプトは機能しません。
採用コンセプトは、全社員が体現すべきメッセージです。社内の理解と共感なくして、求職者への説得力は生まれません。
【社内コンセンサスを形成する方法】
初期段階 | 各部門の代表者を巻き込んだワークショップ開催 |
作成段階 | 定期的な進捗共有と意見収集 |
完成段階 | 全社説明会での背景と意図の丁寧な説明 |
運用段階 | 採用活動への社員参加機会の創出 |
特に重要なのは、なぜこのコンセプトにしたのか、どのような想いが込められているのかを、時間をかけて丁寧に伝えることです。
採用コンセプトでお悩みならコンマルクへ
採用コンセプトの設定は、企業の未来を左右する重要な取り組みです。しかし、自社の魅力を客観的に分析し、競合との差別化を図りながら、求職者の心に響くメッセージを作り上げることは、決して簡単ではありません。
そんな採用コンセプトの設定でお悩みの企業様は、コンマルクにご相談ください。
コンマルクの採用広報コンサルティングでは、貴社の課題やターゲット人材像をヒアリングし、採用における訴求ポイントを洗い出すことで、貴社独自の採用コンセプトを一緒に作り上げます。
自社での採用広報実績(一人あたり採用コスト31.2万円、月平均84件の応募)から、「成長できる環境」「コミュニケーションの取りやすさ」「裁量の大きさ」など、条件以外の価値で選ばれるための採用コンセプトのつくり方を熟知しており、貴社らしい採用コンセプトづくりをサポートします。
コンマルクの採用広報サービスはこちらから
お問い合わせはこちらから
- 採用ブログ・オウンドメディア運用代行
- Wantedly運用代行コンサルティング
- 採用動画制作
- 採用サイト・コンテンツ制作

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。