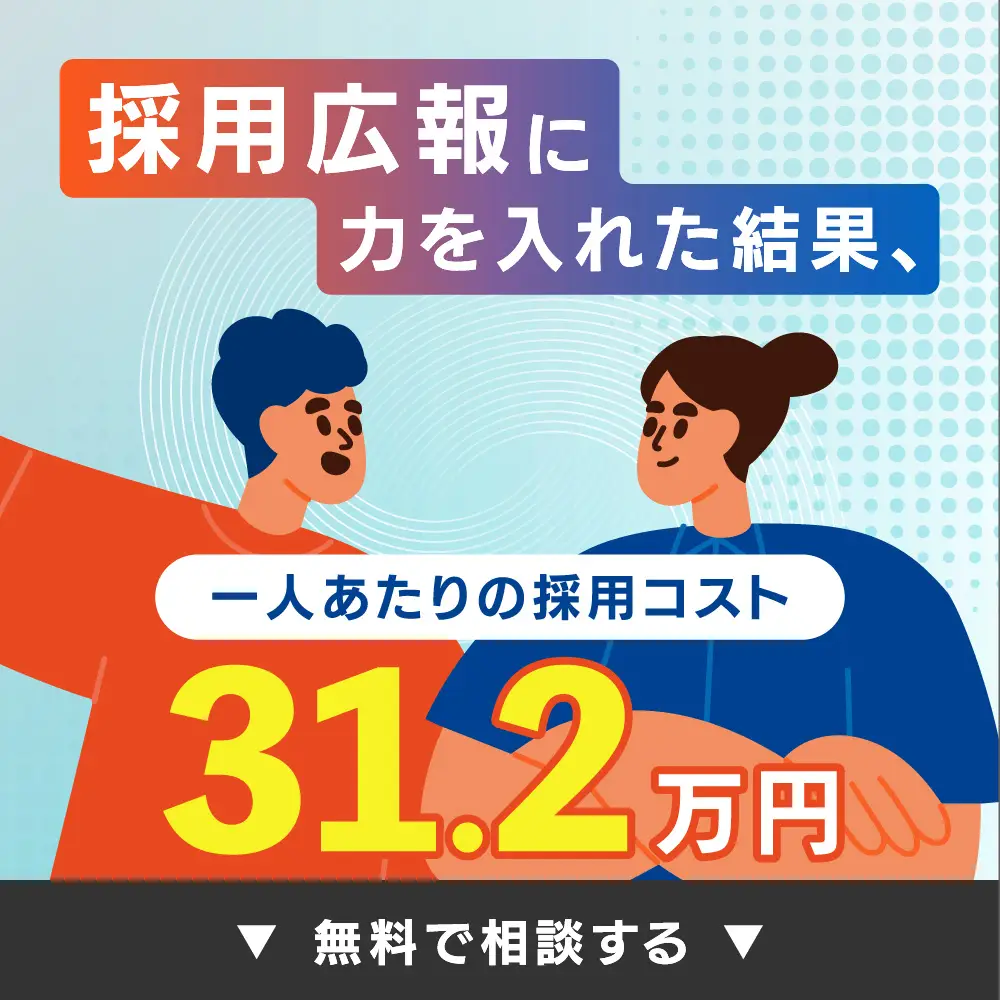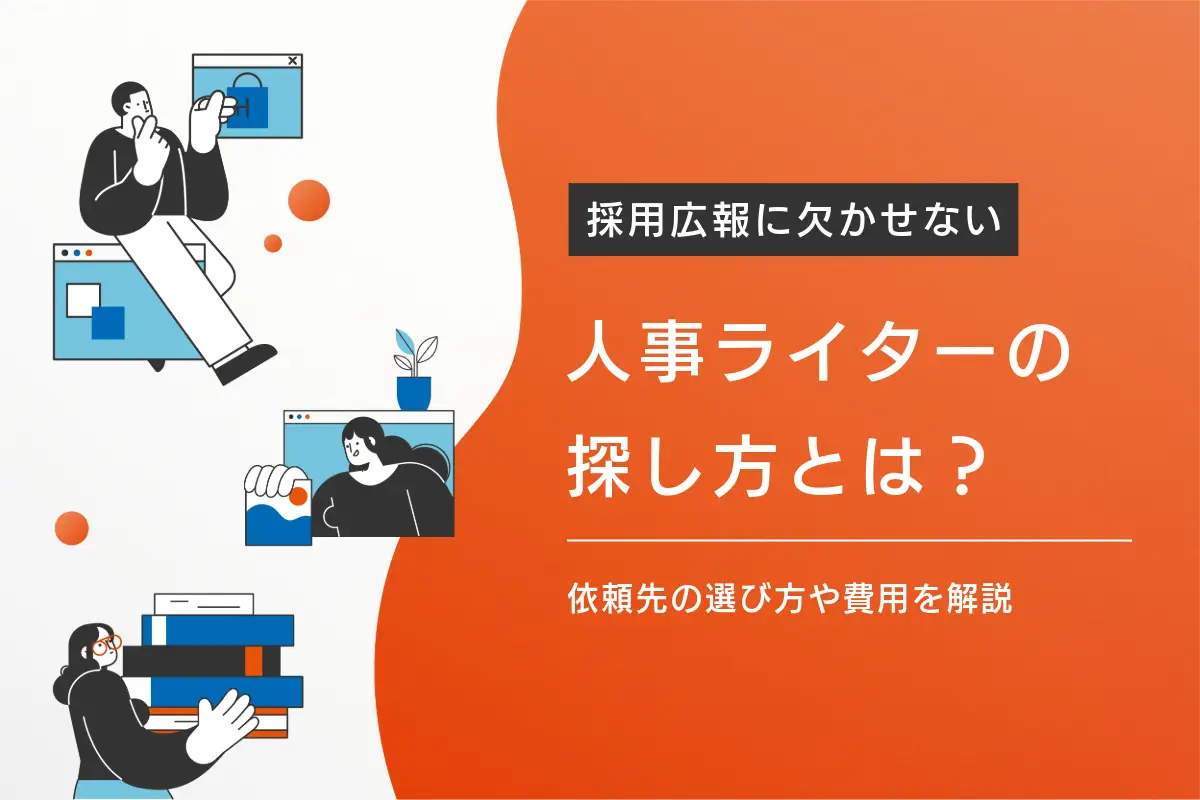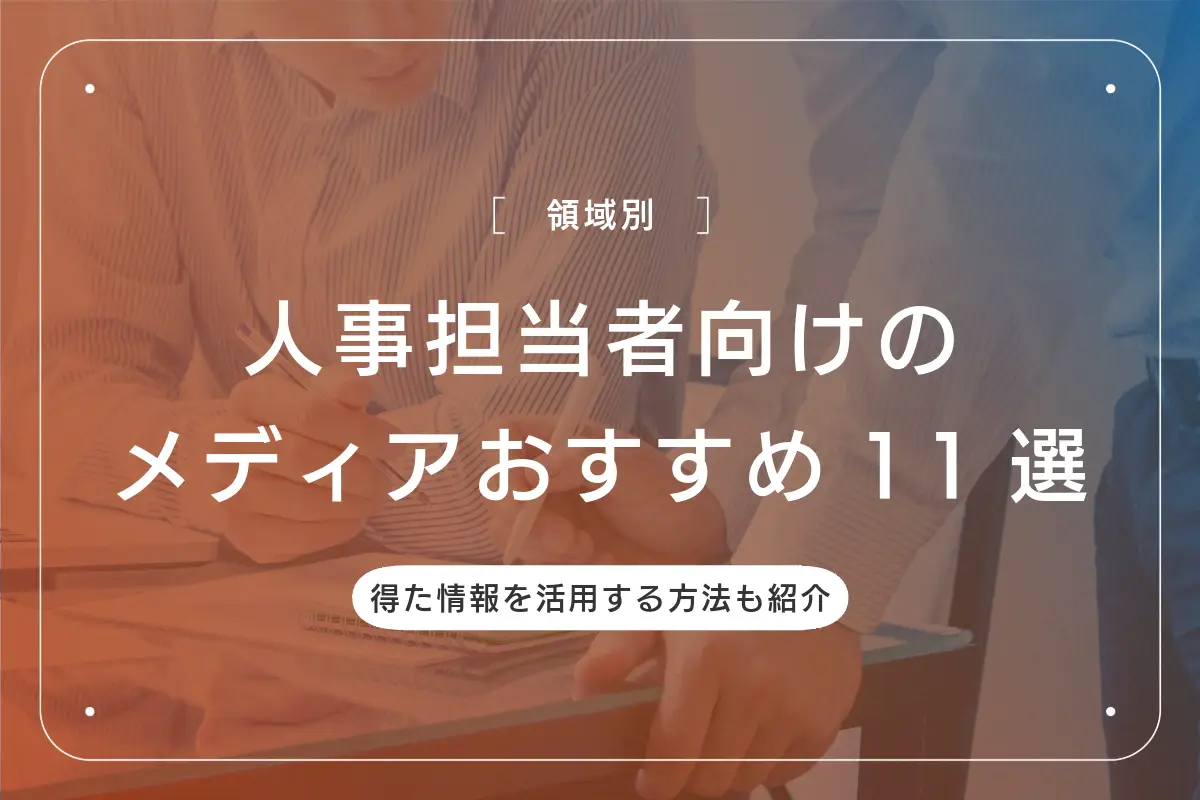採用サイトに必要な12のコンテンツとは?設計の流れについても解説
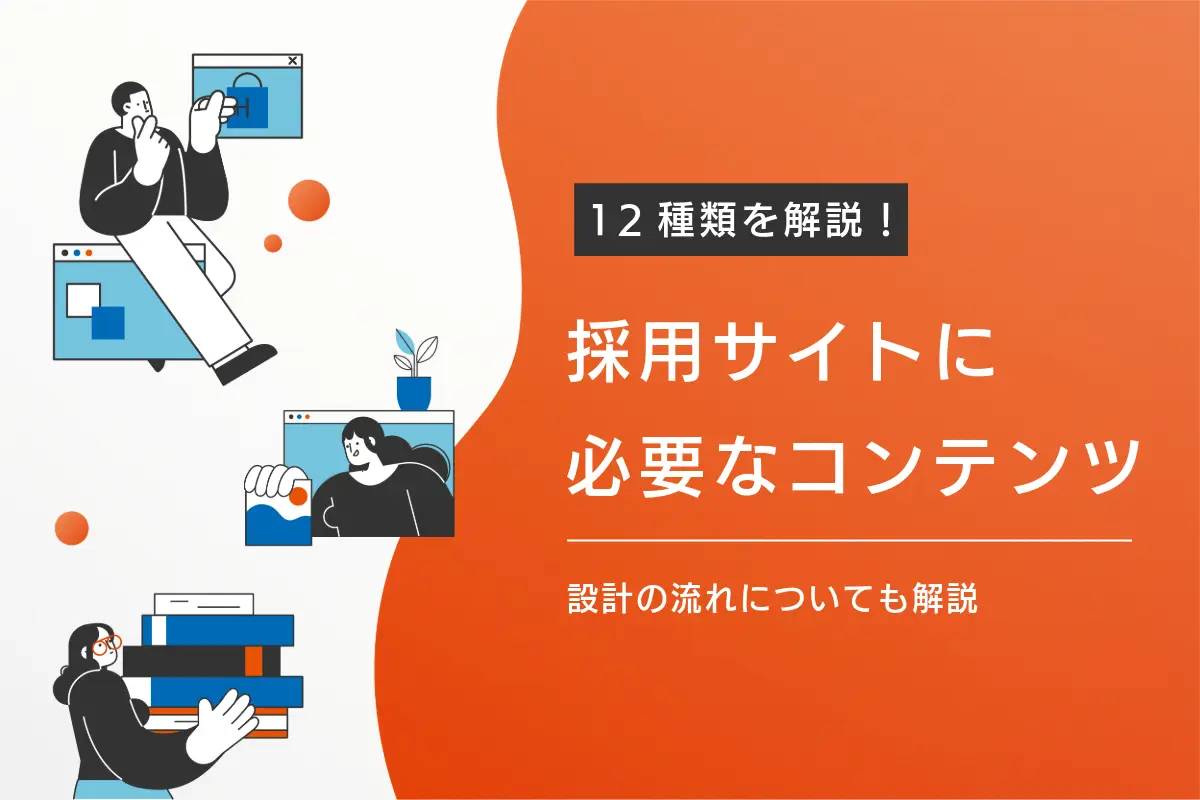
採用サイトのコンテンツは、企業と求職者をつなぐ架け橋です。戦略的なコンテンツ設計により、優秀な人材の獲得と採用ミスマッチの防止を実現できます。
本記事では、採用サイトに必要な12種類のコンテンツと、新卒・中途採用それぞれに適した戦略、成功事例を詳しく解説します。
採用サイトにおけるコンテンツの重要性
求職者の約8割が応募前に企業の採用サイトをチェックしているという事実をご存知でしょうか。いまや採用サイトのコンテンツは、求職者が企業を理解し、応募を決断するための判断材料となっているのです。
効果的なコンテンツがあれば、企業理念や社風への共感を生み出し、入社後の定着率向上も期待できます。さらに、採用サイトは企業ブランディングの役割も果たすことから、競合他社との差別化を図るツールとしても活躍してくれます。
関連記事:採用サイトとは?効果や作り方、成功のコツを事例とともに紹介
採用サイトで必須のコンテンツ
採用サイトには必ず掲載すべきコンテンツがあります。これらの基本情報が不足していると、求職者は応募を躊躇してしまいます。
企業理解を深め、応募意欲を高めるために、以下の8つのコンテンツは必ず充実させましょう。
会社概要・事業内容
企業の基本情報は採用サイトの土台です。設立年月日、資本金、従業員数などの基本データは必須ですが、数字だけを並べても求職者の心には響きません。
創業ストーリーや企業の成長過程は物語として伝えることで、企業への興味を深めることができるでしょう。事業内容を記載する際は専門用語を使わず、どんな価値を社会に提供しているのかを平易な言葉で表現することが大切です。
またグローバル展開している企業なら、海外での活動も具体的に記載することで、スケールの大きさと成長機会の豊富さが伝わります。
募集要項・求人情報
募集要項は求職者が最も注目するコンテンツです。職種名、勤務地、給与、勤務時間などの基本情報は、できるだけ具体的に記載することがポイントとなります。
給与は「当社規定による」ではなく、経験やスキルに応じた目安を示すことで信頼感が生まれます。応募資格は必須条件を最小限に絞り、歓迎条件で理想の人材像を示すことで、より多くの応募を集められるでしょう。
求める人物像では、スキルだけでなく価値観や仕事への姿勢も含めて記載すべきです。入社後にどんな活躍を期待しているのか、具体的なイメージを持ってもらえるような表現を心がけましょう。
選考フロー・スケジュール
選考プロセスを透明化することで、求職者の不安を解消できます。書類選考から内定までの流れを図表で示し、各ステップでどんな評価をするのかを明確にしましょう。
面接回数や面接官の役職、所要時間なども事前に伝えることが大切です。Web面接を実施している場合は、使用ツールや注意点も記載することで、求職者は準備しやすくなります。
また選考期間の目安も重要な情報です。「書類選考は1週間以内に結果連絡」など具体的な日数を示すことで、求職者は他社との選考スケジュールも調整しやすくなります。
企業理念・ビジョン
企業理念は単なるスローガンではありません。日々の業務にどう活かされているか、具体的なエピソードとともに伝えることで、求職者は企業の本質を理解できます。理念が形骸化していないことを示すことができれば、共感する求職者を集められるでしょう。
将来のビジョンについても、抽象的な表現ではなく、具体的な数値目標や事業計画を含めて記載することで、求職者は自分のキャリアと企業の成長を重ね合わせて考えられます。
代表メッセージ
経営者の言葉は、企業の方向性を最もダイレクトに伝えるコンテンツです。形式的な挨拶文ではなく、経営者の人柄が伝わるメッセージを掲載しましょう。
なぜこの事業を始めたのか、どんな困難を乗り越えてきたのか、これからどんな仲間と一緒に働きたいのか。経営者の想いを率直に語ることで、求職者の共感を呼ぶことができます。
写真は証明写真のような堅い表情ではなく、自然な笑顔や仕事中の真剣な表情など、人間味が感じられるものを選ぶことがポイントです。
社員インタビュー・社員紹介
リアルな職場の雰囲気を伝えるには、実際に働く社員の声が最も効果的です。様々な部署や年次の社員に登場してもらい、多様な働き方があることを示しましょう。
インタビューでは仕事の楽しさだけでなく、大変だったことやそれをどう乗り越えたかも含めることで、信頼性が高まります。入社の決め手や、実際に働いてみて感じたギャップなども正直に語ってもらうことが大切です。
写真は仕事中の自然な表情を捉えたものがベストです。デスクワークの様子だけでなく、会議中の真剣な表情、ランチタイムの和やかな雰囲気など、職場の日常が伝わるシーンを選ぶことをおすすめします。
福利厚生・待遇制度
福利厚生は企業が社員をどれだけ大切にしているかを示すバロメーターです。法定福利だけでなく、独自の制度があれば積極的にアピールしましょう。
有給取得率や平均残業時間などの数値データは、実態を正直に公開することで信頼を得られます。育児支援制度があるなら、実際の利用者数や復職率なども併せて掲載すると説得力が増します。
ユニークな制度があれば、その背景にある考え方も説明するとよいです。例えば「誕生日休暇」なら、なぜその制度を作ったのか、社員にどう活用されているのかを具体的に記載することで、企業文化が伝わります。
教育・研修制度
成長機会の提供は、特に若手人材にとって重要な判断基準です。入社時研修の内容や期間、その後のフォローアップ体制を具体的に記載しましょう。
スキルアップ支援制度があれば、どんな研修が受けられるのか、費用負担はどうなっているのかを明確にすることが大切です。また実際に研修を受けて成長した社員の事例があれば、説得力が格段に上がります。
メンター制度やOJTの仕組みについても、形だけでなく実際にどう機能しているかを伝えるようにしましょう。「入社1年目の社員には必ず先輩社員がメンターとしてつく」など、具体的な運用方法を記載することで安心感を与えられます。
採用サイトで差別化につながるコンテンツ
競合他社との差別化を図るためには、基本情報だけでなく独自性のあるコンテンツも必要です。以下のコンテンツを充実させることで、求職者により深い企業理解を促し、入社意欲を高めることができます。
1日の仕事の流れ
多くの求職者が知りたいのは、実際にどんな1日を過ごすことになるのかという点です。職種別に、朝の出社から退社までの流れを時系列で示しましょう。ここでは単なるスケジュール表ではなく、各時間帯の仕事の様子を具体的に描写することがポイントです。
繁忙期と通常期の違いや、リモートワーク時の過ごし方も含めると、より現実的なイメージを持ってもらえます。写真や動画で実際の職場の様子を見せることも効果的です。
キャリアパス・評価制度
将来のキャリアイメージを明確に示すことで、成長意欲の高い人材を惹きつけられます。入社後にどんなステップでキャリアを積めるのか、複数のパターンを提示すると良いでしょう。
評価制度は透明性が命です。何を基準に評価するのか、どんなプロセスで昇進・昇格が決まるのかを明確に記載することで、実力主義の企業文化をアピールできます。
実際に活躍している社員のキャリアストーリーを紹介するのも効果的です。「入社3年目で課長に昇進したAさん」など、具体例があることで、求職者は自分の将来像を描きやすくなります。
数字で見る会社データ
平均年齢、男女比、有給取得率などのデータを視覚化することで、企業の実態を客観的に伝えることができます。
ただし、ただ数字を並べるだけでなく、その数字が持つ意味を解説することが重要です。例えば「平均年齢32歳」なら、若手が活躍できる環境であることや、ベテランとのバランスが取れていることなどを併せて伝えると良いでしょう。
よくある質問(FAQ)
FAQは求職者の不安や疑問を先回りして解消するコンテンツです。実際に寄せられた質問をベースに、カテゴリー別に整理して掲載しましょう。
質問への回答は、建前ではなく本音で答えることが信頼につながります。例えば残業について聞かれたら、「月平均20時間程度ですが、繁忙期は40時間を超えることもあります」と正直に答えたうえで、改善への取り組みも併せて伝えると好印象です。
最新の働き方トレンドを反映した質問も重要です。「副業は可能ですか」「リモートワークの頻度は」など、時代のニーズに応える情報を積極的に掲載することで、柔軟な企業姿勢をアピールできます。
採用コンテンツ設計の流れ5ステップ
ここでは、採用サイトのコンテンツを設計する流れを5つのステップで解説します。
1. 採用ターゲットを明確化する
まず、どのような人材を採用したいのか、ペルソナを具体的に設定しましょう。年齢、スキル、価値観、キャリア志向などを詳細に定義することで、ターゲットに響くコンテンツを企画できます。
ターゲット設定では、必須条件と歓迎条件を明確に分けることが大切です。また、自社で活躍している社員の特徴を分析し、成功パターンを見出すことも有効な手法となります。
2. 採用サイトの目的を定義する
続いて、採用サイトが果たすべき役割を明確にします。認知拡大、興味喚起、応募促進、入社意欲向上など、採用プロセスのどの段階で、どのような効果を期待するのかを定義しましょう。
目的が明確になれば、必要なコンテンツの優先順位も自然と決まってきます。限られたリソースを効果的に活用するためにも、この段階での検討は欠かせません。
3. 求職者のニーズを調査・分析する
採用サイトの目的が決まったら、次はターゲットとなる求職者が企業選びで重視するポイントを調査するステップです。アンケートやインタビュー、Web解析データなどを活用し、求職者の情報ニーズを把握しましょう。
特に、内定辞退者や選考離脱者からのフィードバックは貴重な情報源です。なぜ自社を選ばなかったのか、どんな情報が不足していたのかを分析することで、コンテンツ改善の方向性が見えてきます。
4. コンテンツマップを作成する
収集した情報をもとに、サイト全体のコンテンツ構成を設計するステップです。情報の優先順位、ページ間の導線、ユーザビリティなどを考慮し、求職者が必要な情報にスムーズにアクセスできる構造を作りましょう。
このとき、モバイルファーストの設計にすることも重要なポイントです。スマートフォンでの閲覧を前提に、タップしやすいボタン配置や読みやすいフォントサイズなど、モバイルユーザビリティを最優先に考える必要があります。
5. 効果検証・改善を繰り返す
採用サイトは作って終わりではありません。アクセス解析ツールを活用し、ページビュー、滞在時間、応募率などのデータを定期的に分析しましょう。
改善のサイクルを回すことで、より効果的なコンテンツへとブラッシュアップしていきます。A/Bテストを実施し、どのようなコンテンツや表現が求職者に響くのかを検証することも大切です。
新卒採用と中途採用でのコンテンツ戦略の違い
新卒採用と中途採用では、求職者の関心事や重視するポイントが大きく異なります。それぞれの特性を理解し、ターゲットに合わせたコンテンツ戦略を立てることが、採用成功の鍵となります。
新卒採用サイトで重視すべきコンテンツ
新卒学生は社会人経験がないため、企業文化や成長環境、教育体制などに高い関心を示します。将来のキャリアビジョンを描けるような情報提供が求められます。
新卒採用サイトで特に重視すべきコンテンツは以下の通りです。
入社後の研修制度
企業文化・職場環境
キャリアパスの多様性
これらのコンテンツを充実させたうえで、専門用語を避け、インフォグラフィックや動画コンテンツを活用して視覚的に訴求することが新卒採用サイトでは重要なポイントとなります。
中途採用サイトで重視すべきコンテンツ
中途採用の求職者は、即戦力としての活躍を期待されるため、具体的な業務内容や待遇面での情報を重視します。
中途採用サイトで特に重視すべきコンテンツは以下の通りです。
詳細な業務内容・必要スキル
中途入社者のキャリアパス事例
給与・待遇の透明性
ワークライフバランスの実態
これらの情報を通じて、転職による収入やキャリアの変化を具体的にイメージできるようにすることが重要です。特に、実際の社員の働き方事例を交えて説明することで、入社後の生活をリアルに想像してもらえます。
採用コンテンツの制作ならコンマルクにご相談を
採用競争が激化する中、効果的なコンテンツ戦略は企業の採用力を大きく左右します。本記事で紹介した12種類のコンテンツと設計手法を参考に、自社の魅力を最大限に伝える採用サイトを構築し、優秀な人材の獲得を実現しましょう。
しかし、質の高い採用コンテンツを継続的に制作し、効果的に運用していくことは、企業にとって大きな課題となっています。社内リソースの不足、コンテンツ制作のノウハウ不足、効果測定の難しさなど、採用広報を本格的に展開するにはハードルが高いとお考えの企業様も多いことでしょう。
そのような採用広報の課題を抱える企業様におすすめなのが、コンマルクの採用広報サービスです。
私たちコンマルクは、自社の採用広報に力を入れ続けた結果、一人あたりの採用コストを31.2万円まで削減(業界平均103.3万円)。自社サイトとWantedlyだけで月平均84件の応募を獲得し、Wantedlyフォロワー数は日本第7位を達成しました。
この経験とノウハウを活かし、お客様の採用課題に合わせた最適なコンテンツ戦略をご提案します。
【コンマルクの採用広報サービスの特徴】
自社で採用コストを70%削減した実績とノウハウを提供
インタビューから撮影、記事作成まですべて代行で人事担当者の負担を最小限に
制作コンテンツはWantedly、SNS、スカウトメールなど様々な場面で使い回し可能
応募者の90%が事前にコンテンツを読み込んでから面接に臨む効果を実証済み
詳しくは以下よりお問い合わせください。
コンマルクの採用広報サービスはこちらから
お問い合わせはこちらから
- 採用ブログ・オウンドメディア運用代行
- Wantedly運用代行コンサルティング
- 採用動画制作
- 採用サイト・コンテンツ制作

SEOコンテンツディレクター・ストラテジスト。5,000記事以上のコンテンツ制作実績をもち、製造業から美容、テクノロジーまで幅広いジャンルにて集客・リード獲得実績多数。株式会社GIGの運営するLeadGrid Blogにて初代編集長を務める。コンマルクでは、SEOを軸としたコンテンツマーケティング戦略とWebマーケティングの実践知を発信する。