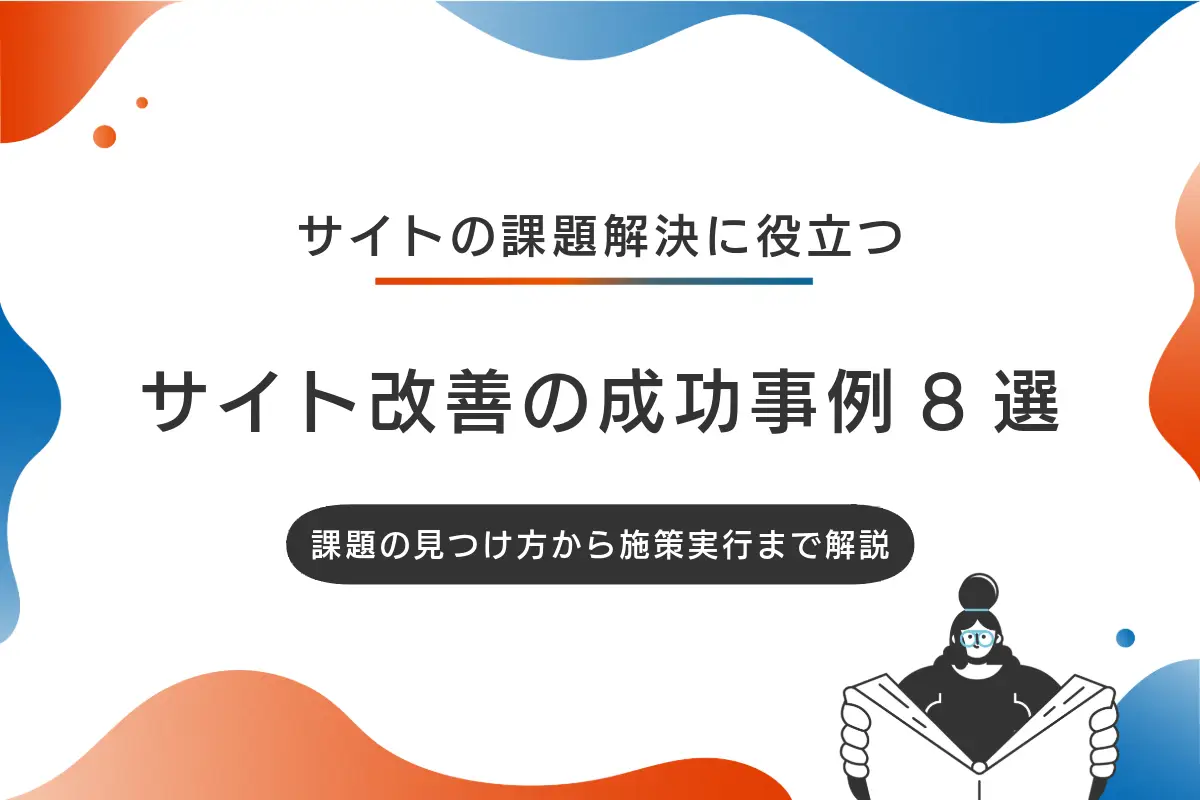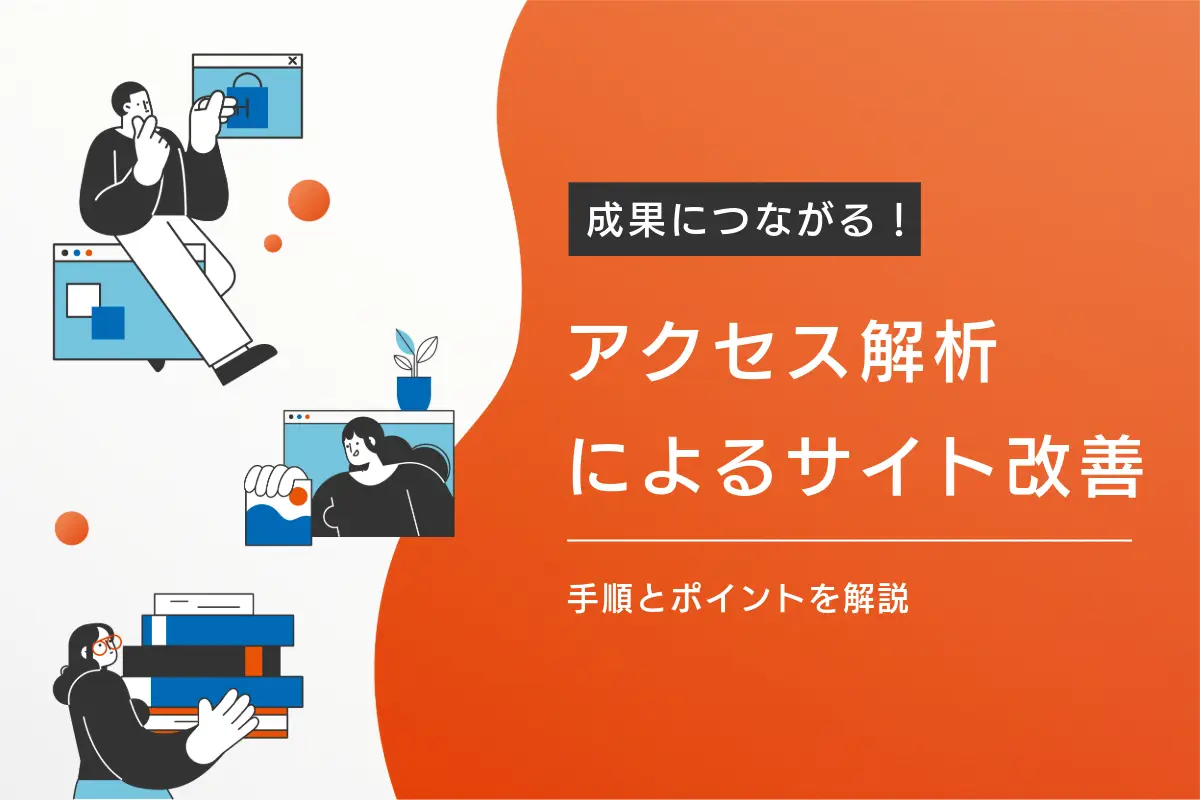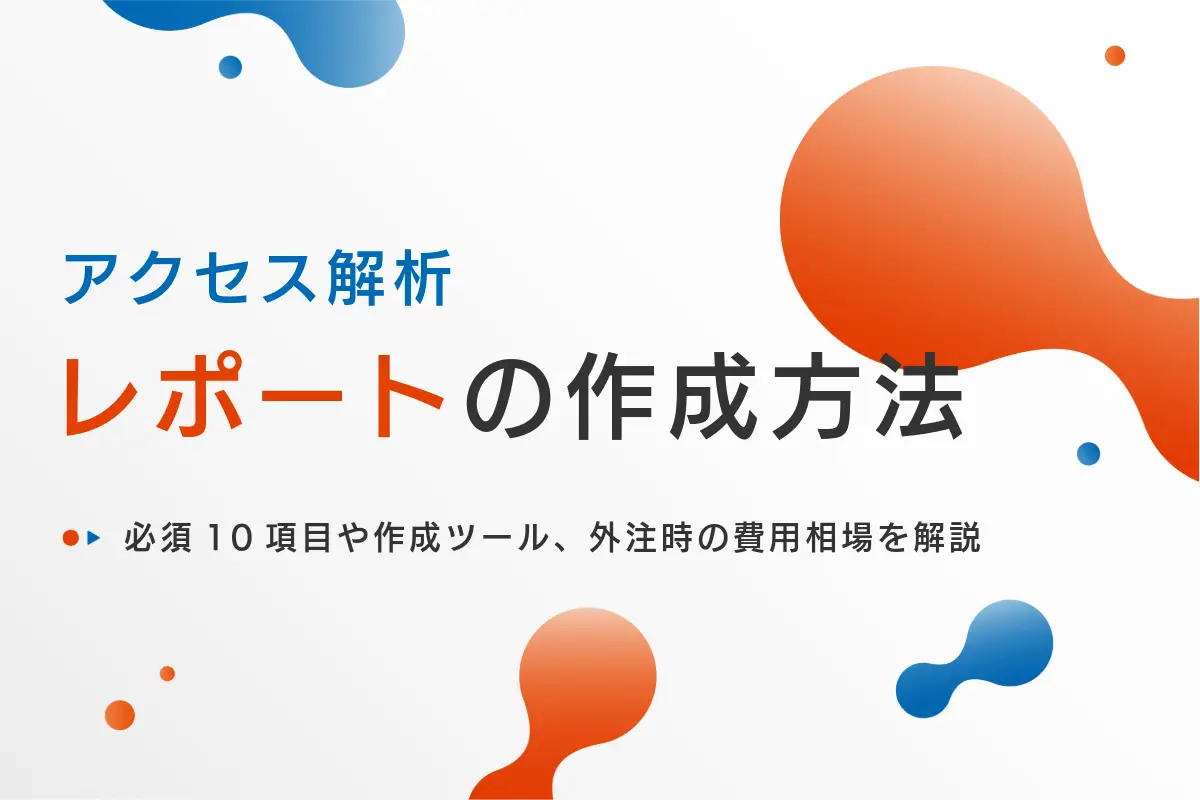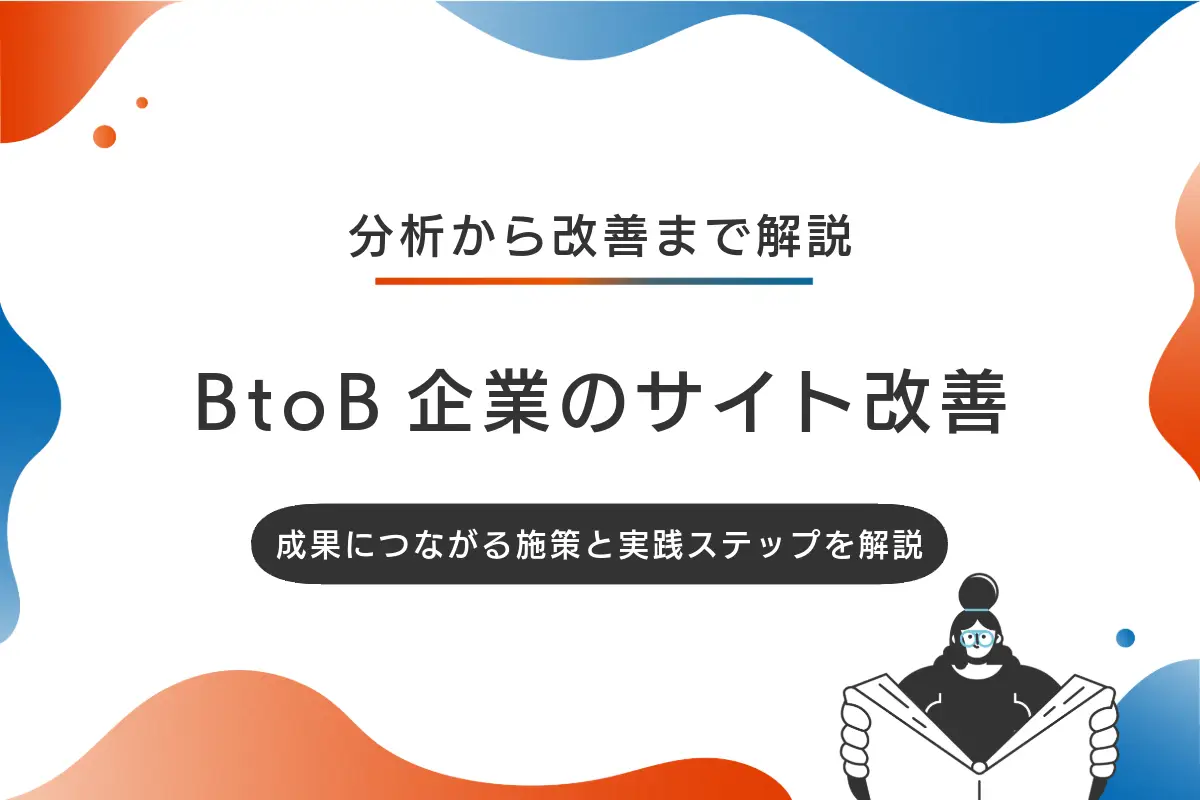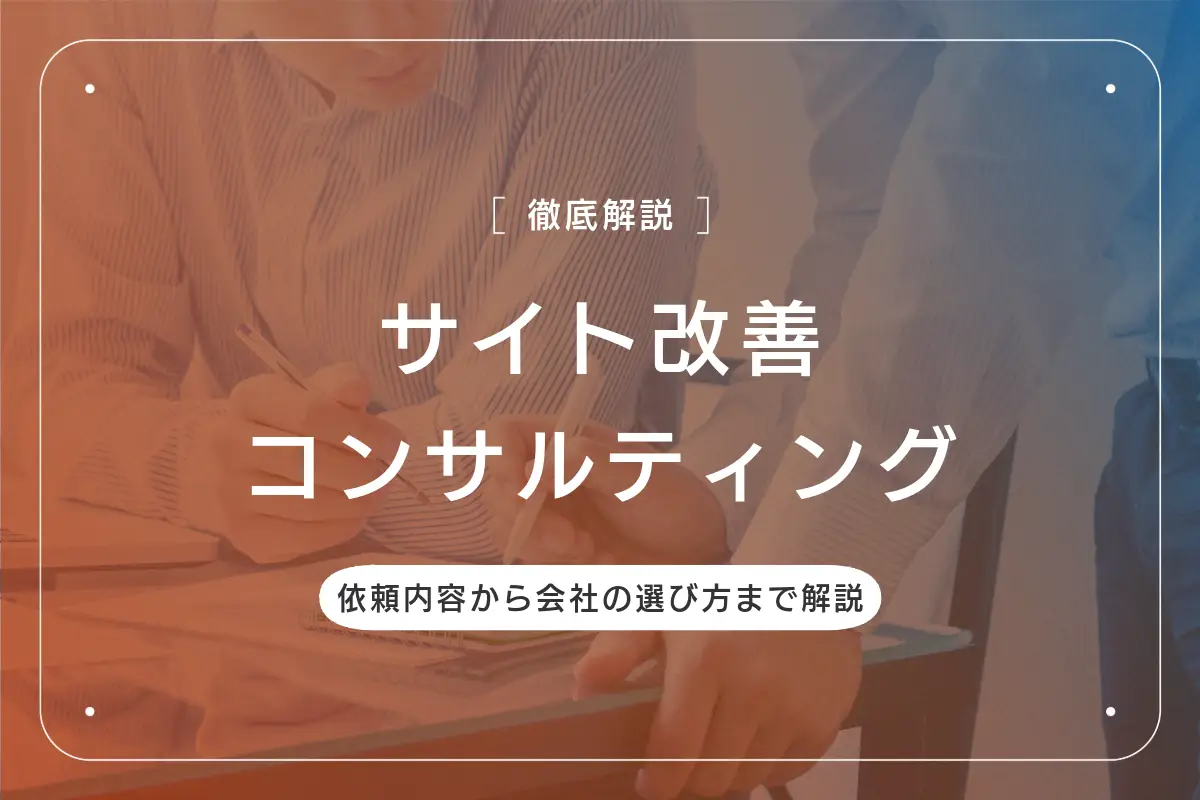AI検索(LLMO)時代のKPIはどう設定する?定量的なKPIよりも「言及されている内容」が重要な理由
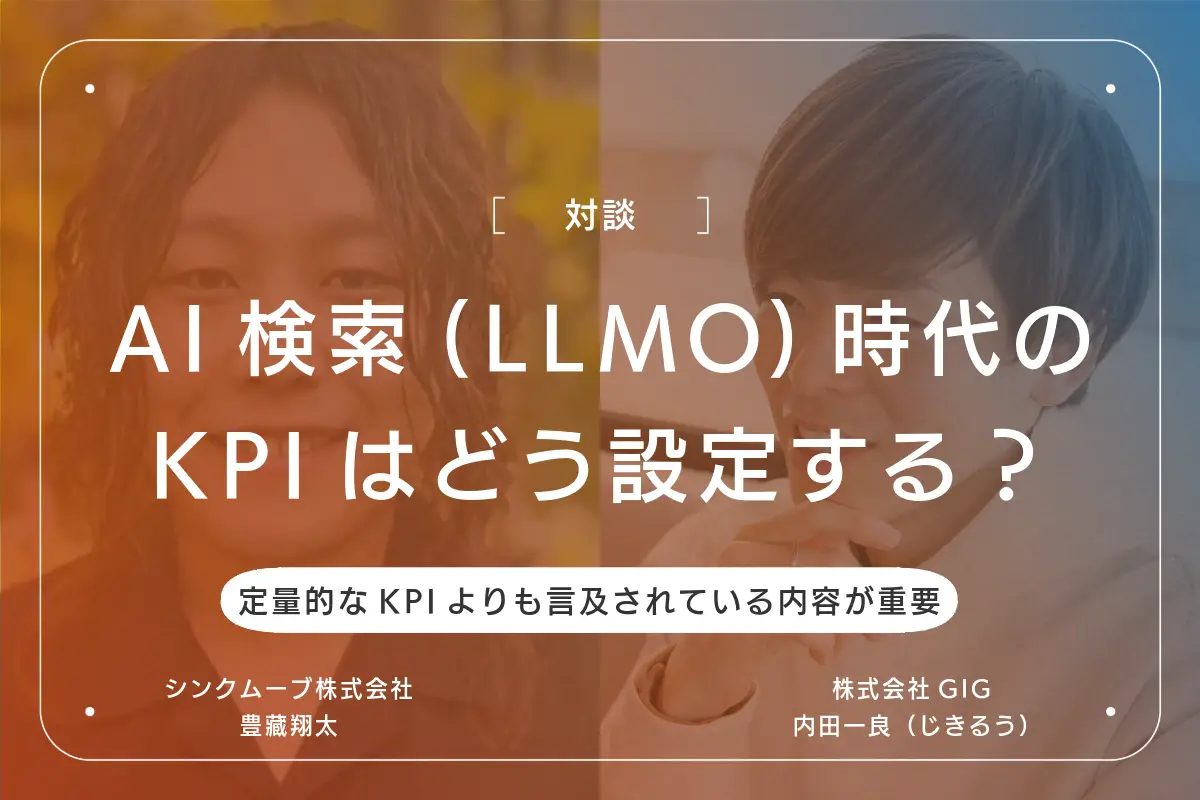
AI検索の台頭により、マーケティングの常識は大きく変わろうとしています。特に、施策の効果を測るための重要業績評価指標(KPI)の設計は、多くの担当者が頭を悩ませる課題でしょう。今回は、マーケティングの専門家である豊藏翔太氏と内田一良(じきるう)氏のお二人に、この変化の激しい時代におけるKPIのあり方について語っていただきました。
豊藏 翔太 (とよくら しょうた)
1992年生まれ。人材系営業、ITコンサルタント、Webコンサルティング事業責任者を経て2024年12月にシンクムーブ株式会社を設立。SEOとAIとファシリテーション経験を活かした「インハウスマーケティング共創支援サービス」を展開。著書「AI時代のSEO戦略──組織を動かし成果を引き寄せる実務マネジメント」アイオイクス株式会社フェローを兼務。
内田 一良 (うちだ かづよし/じきるう)
早稲田大学および同大学院卒。株式会社GIGにてMarketing事業部長。Workship、LeadGrid、コンマルクなどの自社プロダクトマーケから顧客支援まで行う。複数メディアの編集長を経験し、これまで5,000記事以上の編集・ディレクションに携わる。書籍『デザインの言語化』『フリーランスの進路相談室』『ADHD会社員、フリーランスになる。』『マンガでわかる!フリーランスの生き残り戦略』などの監修・編集も。
AI検索では「KPIを設定する」という考えを見直すべき
豊藏: クライアントワークでKPI設計の話をする機会が非常に多いのですが、AI検索の時代になって、KPIを考えすぎないほうがいいのではと考えています。
そもそもKPIという考え方は、既存の成功法則が通用したり、環境の変数が安定していたりする時に有効なものだと思うんです。例えば「他社が半年で10万セッション達成したから、うちも同じ方法でいけるだろう」といった予測ですね。
しかし、今のAI検索、特にAI Overview(SGE)などは、表示回数が毎月のように変わる。この状況で従来のKPIだけを見ていると、「KPIのための仕事」ばかりが増えてしまうと感じています。
内田: まったく同感です。SEOであれば一度1位になればしばらく安定しますが、AI検索は検索するたびに、それこそ1分後には結果が変わることもあります。しかも、ChatGPT、Gemini、Perplexityなど、どのAIを使うかでも結果はバラバラ。これでは追いかけようがありません。
AI検索の効果測定は「決め打ち」と「短期視点」
内田:AI検索の効果測定は、測定対象と測定ツールを絞ることが重要だと考えています。例えば、「AI検索の中ではAI OverviewとChatGPTだけを追いましょう」「ツールはAhrefsの数値に従いましょう」といった具合です。AI検索はまだまだ流動的な分野であり、ある程度決め打ちしないと計測もままならないので……。
豊藏:測定対象と測定ツールを絞ることは非常に重要だと思います。その上で、KPIを中長期で設定するのはやめた方がいいかもしれません。施策に取り組んだ当月と前月を詳細に比較するなど、KPIを見る期間をもっと短くすべきだと感じています。未来の予測としてのKPIよりも、変化の前後をしっかり捉えることが重要です。
内田:特にLLM(大規模言語モデル)周りは、計測ツール自体の基準もどんどん変わっていますからね。Ahrefsも対応するクエリを拡充している最中で、今月と来月では得られる情報が全く違う。長期で見るのは僕も不可能だと思います。
豊藏:そうなんです。ツールのデータベースも日々更新されているので、その数値を絶対的な指標にするのも難しい。今、AI検索は「一体何を持って測ればいいのか分からない」という状態です。
AI検索で「どのように言及されているか」が最重要
内田:GIGとして大事にしているのが、定量的な成果よりも「AI検索で得られた情報の中身」です。例えば「ChatGPTで100回表示されました」という件数よりも、「自社ブランドがどのような文脈で、どのように言及されているのか」という定性的な内容の方がはるかに重要だと考えています。
豊藏:定量的な成果に囚われすぎると、変化が速い時代に前例踏襲に陥るリスクがあります。「このプロジェクトはKPIを追うべきなのか、それともKPIが必ずしも正しくないプロジェクトなのか」を見極める必要があると感じます。
内田:とはいえ、決裁を取るためには予測や計画が必要で、どうしてもKPIを設定せざるを得ない場面も少なくありません。その場合は、まずブランド側の意図とAIによって生成された実際の言及内容のギャップを可視化します。例えば、「高品質で顧客対応が良い」と認知されたいにも関わらず、生成AIでは「価格が安い」と言及されているなどです。
そして「このギャップを埋めるために、こういう施策をやりましょう」と定性的な目標とセットで提案し、その出したいブランドイメージに沿った言及数を追っていくという形ならKPIを設定できると考えています。
AI検索からの流入は「副産物」
内田: そもそもAI検索やLLMへの対応自体が、ある種のチャレンジングな取り組みだと捉えています。既存のSEOや広告でしっかり基礎集客しつつ、LLM対応に今から準備するという形が適していると思います。
豊藏: 大手企業が既存事業でキャッシュを作りながら、新規事業に投資するのと同じ構図ですね。最初から当たる新規事業を見つけるのは難しい。全体の業務や予算の中で、挑戦する部分をどう設計するかが重要です。この視点がないと、業界全体が縮小していってしまう恐れがあります。
内田: AI検索最適化(LLMO)の成功事例を見ても、新しい挑戦から生まれていますからね。そこに保守的なKPIを組んでいくのはナンセンスです。それに、AIに言及されたからといって、クリックが爆発的に増えるわけでもない。せいぜい1〜2%程度です。
とはいえ、「ChatGPTで見て問い合わせました」というケースは確実に増えています。弊社の「Workship」というフリーランス・副業向けマッチングサービスも、今年に入って登録者が急増した要因の一つが、ChatGPT経由での認知でした。
豊藏: そのお話は本質的ですね。Workshipの事例はおそらく、最初からLLMでの流入を狙ったわけではないですよね。良いプロダクトを作り、サイトをしっかり運用・改善した結果、副産物としてLLMでの言及が増えた。
内田: 全く狙っていませんでした。結局、プロダクトが良くないと話にならないし、そのプロダクトが外部からどう認知されているかという広報・PR的な視点が、これまで以上に重要になっていると感じます。
関連記事:AI検索時代を勝ち抜くために「マーケティングと広報の融合」が大切な理由
安易なKPI設計がブランドイメージを毀損させる
内田: AIによる言及を最終目標に置くなら、その手前にある外部メディアでの言及数やサイテーション(引用・参照)を先行指標としてKPIに設定するのが現実的かもしれません。
豊藏: ただし、プレスリリースのPV数を増やすために、ブランドイメージを損なうような施策を打っては本末転倒ですよね。
内田: まさに。定量的な指標だけでなく、定性的なものを一緒に測っていくことが絶対に必要です。そこを見ないと、「言及は増えたけど、ブランドイメージはボロボロになった」という最悪の事態になりかねません。アフィリエイト施策で、「ブランド名 やばい」というキーワードでの言及が増えてしまう、なんていうのは"あるある"ですよね。
自社ブランドをどう見せたいかを軸に、定量と定性の両面から指標を設計し、リスクを管理していく。この複雑な舵取りこそが、これからのマーケターに求められるスキルなのだと思います。
AI検索最適化についてコンマルクに相談してみる
コンマルクでは自社メディア運用のノウハウを活かし、お客様のAI検索最適化をサポートしています。AI検索最適化の設計から制作、運用まで、一気通貫で支援できます。
「AI検索最適化のKPIを設定したい」「ブランドイメージとAIの言及のギャップを埋めたい」などAI検索最適化でお悩みの方は、ぜひコンマルクにご相談ください。
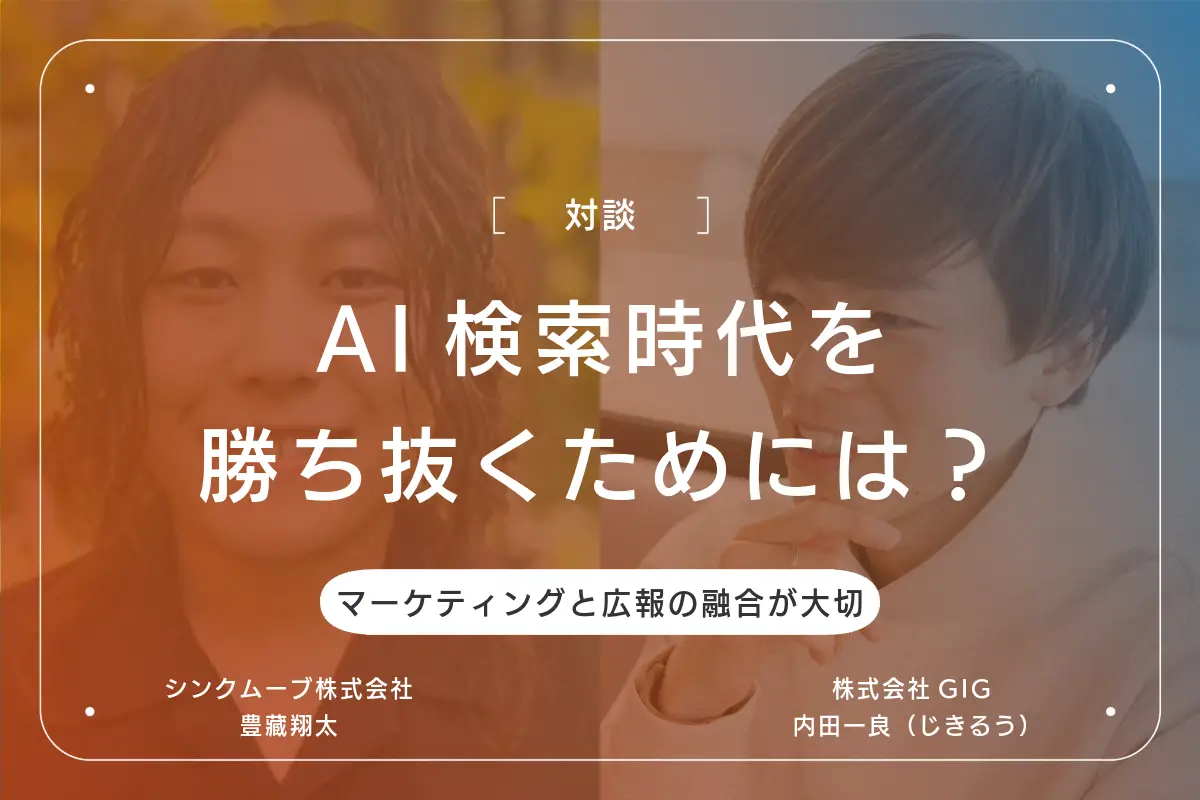
- インタビュー記事制作 / 設計
- SEOコンテンツ制作 / 設計
- ホワイトペーパー制作 / 設計
- 動画制作 / 設計
- アクセス解析基盤設計
- アクセス解析・Webコンサルティング
- Web広告・SNS広告
- コンセプト / ペルソナ / CJM設計
- コンテンツマーケティング伴走支援 など

立命館大学政策科学部卒。学生時代より学生起業家へのインタビューや就職活動に関するメディアを運営。株式会社GIG入社後はウェブ解析士の資格を取得し、自社メディア「コンマルク」の編集長業務、SEO記事制作、アクセス解析、Webマーケティングに関するレクチャーまで幅広く担当。